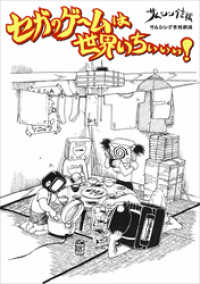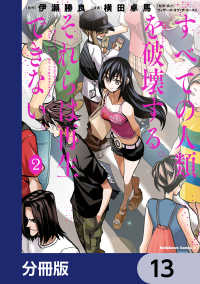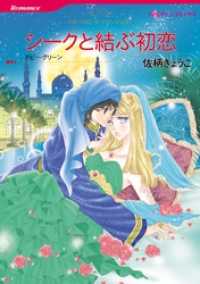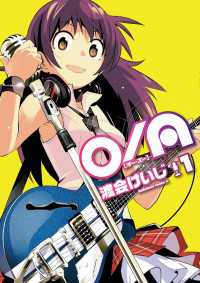内容説明
本書は、メディアアートの実践者として、 また教育者として、最先端を走り抜けてきた久保田晃弘が、脱中心(=固着した人間中心主義から脱却すること、すなわち人間、ひいては社会が変わることを前提とした経験的想像力を超えたものづくり)を志向しながら、工学から芸術へ、「設計」から「デザイン」へと展開した、20年にわたる思索と実装を辿るデザイン論集です。
いま、何をつくったらいいのか?
見たことのないものを、なぜ人はつくれるのか?
真に新しいものをつくりだすということは、どういうことなのか?
人工知能が超知能になるポスト・ヒューマンの世界を見据え、デザイナーは足元に穴を掘り続けるのではなく、遠くへ行くための道をつくらなければなりません。「科学技術が社会に普及浸透していくためには、文化的、芸術的なアプローチが必要不可欠である」という視点から出発し、「一体何が、これからのデザインや芸術になり得るのか?」を常に探求してきた久保田の予見に満ちた言説は、テクノロジーとともに更新されゆく私たち人間、そして社会の未来を鮮やかに照らし出します。
目次
第1章 芸術から身体へ
第2章 素材から即興へ
第3章 コードから知覚へ
第4章 細胞から宇宙へ
第5章 人間からの離脱
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
袖崎いたる
8
非線形的に訪れない他者への配慮。こだわりのアブダクション。知識論やら言語学やらをこの認識に詰め込む態度。エーデルマンの認知意味論。意味が肉の中に芽生えること。まず感覚することで、訪れるお客様のために空席を支度しておく。〈未-来〉の他者への配慮は〈既-在〉の自己への配慮と一致している。2017/08/31
としあき
0
理解できたかどうかは別として読み物として面白かった。難しくて飛ばしてしまった部分もある。 遥かなる他者というのがまさか人間ではない知性のことだとは思わなかった。2017/08/22
ほしそらねこちゃ
0
手に掴めそうなところでこちらの理解をすり抜けてゆく刺激的なテキスト群2017/03/16
rincororin09
0
石にかじりつく感じで読んだ。難しかった。ちゃんと第三者に説明できるようなレベルでは理解はできてないが、やろうとしていることの方向はわかるような気がする。あちこちにギラッと光る言葉が散りばめられている。すごい人だ。2017/03/17
doji
0
ものすごくエキサイティングな内容というか、個人的にずっとひっかかっていたことがクリアになりそうな本だった。これはデザイナーやエンジニアというより、ミュージャシャンによるミュージシャンが読むべき本だろうと思う。ノーマンをはじめとする人間中心主義への疑義は、しばらくはビジネスやデザインの領域では語られにくいことなのかもしれないけれど、アートがそれを実践していけばいいと思う。2018/04/13