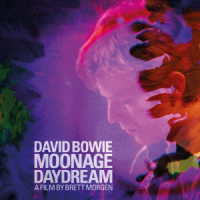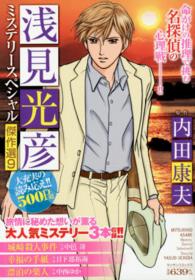内容説明
近代日本は、憲法にもとづく国家体制の確立と東アジアへの勢力拡張とを、ともにごく限られた期間のうちに成し遂げた。だが、歴史の複雑な流れを丹念によみとけば、「立憲」化と「帝国」化の歩みが、つねに同時進行していたわけではないことが分かる。じつは、立憲勢力が軍部らの暴走を効果的に抑え込み、日中対立の激化に抵抗した時期も少なくないのだ。戦前の政治体制のもと、そのような抵抗はいかにして可能であったのか? そして、それにもかかわらず、最終的にこの国の民主主義が対外侵略を阻止しえなかったのはなぜなのか? 悲劇的結末にいたる道を選ばざるをえなかった真因を、第一人者が明らかにする。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
樋口佳之
27
自分が心の底では軽んじてきた中国との戦争に正面から反対する気持ちにはなれなかったのです。同様のことが今日の平和主義者にも起こるのではないか。このような懸念こそが、筆者をして戦前日本の日中関係史の分析に向かわせました。/終章思いの外の熱い議論でした。2018/07/05
小鈴
23
「内に立憲、外に帝国」のダブルスタンダードで同時進行した歴史像ではなく、「帝国」に対抗した「立憲」との関係から歴史像を描く。日中関係に限定しているため勉強になるし、中国を侮り見誤る姿は戦前も今も変わらないと感じました。大御所に意見するのもアレですが、時代区分ごとにゲームのルール(大日本帝国憲法制定前/後、統帥権と対抗する諸権限)を図などで示して描いた方が分かりやすい。戦前の政党史を多少は知らないと読むのが苦痛になるので、人を選ぶ作品なのが残念だ。2017/10/16
勝浩1958
18
副題にあります”日中戦争はなぜ防げなかったか”の問いには、中国側にとっての日中戦争は「民族解放戦争」であり、侵略者日本軍を国土から駆逐することが目的であったので、日本軍の無条件全面撤兵を前提としない講和はまやかしでそれに応ずることは敗北を意味したのである。よって、日本は中国軍民の「殲滅」を選択したが、開戦2年で長期持久戦に方針転換した。筆者は和平への責務は為政者であるといい、リベラルな政党内閣か準政党内閣の下でしか、戦争は抑え込めないと主張しています。2017/11/05
coolflat
12
近代日本が対外進出に着手したのは、1874年の台湾出兵からであり、他方、近代日本が立憲制の導入に向けて具体的な一歩を踏み出したのは、その翌1875年の立憲政体樹立の詔勅からだった。前者を「帝国」化、後者を「立憲」化と呼ぶとするなら、筆者は「立憲化が盛んな時には、帝国化が抑えられる」ということを日本近代史の中に見出したという。例えば、帝国の膨張過程は、1874年の台湾出兵→1894年の日清戦争(1904年の日露戦争)→1915年の対華21カ条の要求→1931年の満州事変→1937年の盧溝橋事件、を辿った。2018/02/07
ケニオミ
12
明治以降の歴史の立場から見て「立憲」と「帝国」は交互に伸長・衰退してきたことを著した書です。些細な失敗が勢力の衰退を招くため、慎重な行動求められます。改めて近衛文麿の優柔不断さが日本にもたらした罪過が目につきました。また、歯車が「帝国」に向かないような仕組みづくりの重要性にも気付かされました。その点安倍首相は危険人物ですね。2017/10/15