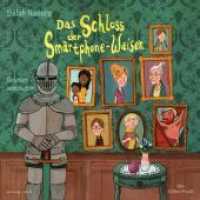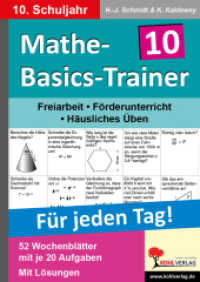内容説明
昭和20年5月、九州上空にて、海軍戦闘機「紫電改」の体当たりによって墜落したB29爆撃機の飛行士12名。彼らは大きなケガを負うこともなく、捕虜になった。しかし、戦局の悪化と度重なる空襲により、捕虜の処遇に困っていた西部軍司令部は、九州大学医学部OBの軍医に処置を一任する。やがて、飛行士たちのうち8名が九大の解剖室に運ばれ、「肺摘出」「心臓摘出」「脳の切開」といった医学実験の犠牲となった。しかも、生きたまま麻酔を打たれ、輸血に代わる「海水注射」も打たれながら……。人間の命を救う立場にある医者が、なぜ凄惨な行為を行ったのか。責任は軍部にあるのか、医者にあるのか。原爆で死んだことに偽装した事件が、なぜアメリカにばれたのか。そして戦犯裁判の結末は? 戦後、日米を震撼させた悲劇の真相を克明に追ったノンフィクション。昭和54年の発売とともに大反響を呼んだ名著が、戦後60年目に甦る!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
fwhd8325
64
「九州大学生体解剖事件」は鳥巣さんを中心に描いていましたが、こちらは全体像を描いています。どちらも、読んでいてしんどい内容です。戦争が人を狂気へと走らせるのか、元々そうした要素を持っているのだろうか。まだ関係者の多くが存命だった時代に書かれた著書だから、軋轢や妨害も想像以上のものだったと思います。戦争に負けると言うことはこういうものなんだと思う一方で、万が一勝利していたらと考えるとそちらの方が怖い。2021/07/14
harass
47
「海と毒薬」の九大生体解剖事件はそういうことがあったとだけ知っていたが細部など全く知らずにいたのでこれに目を通す。裁判の公判記録が発見され、著者が当時生存していた当事者たちにインタビューをする。戦中の福岡市で撃墜され捕虜になった米国飛行士8名、軍医の一人が彼らを解剖しようと提案。大学主導で実験などを行う。戦後軍も絡んで隠蔽工作、広島原爆で死亡したとしたが、GHQが調査し裁判に。軍の命令に従っただけというわけでもなく、手術などに拒否したものも多数いた。「空気」、なんとなくな意思決定かという印象。日本的?2025/12/06
東京には空がないというけれど・・・
8
この本を読むのに結構時間がかかった。登場人物が多いため、何回も頭の中を整理した。意外な発見もあった。米軍検事が、肝臓試食事件をでっちあげていたこと、看護部長がスガモプリズンで東京ローズと交流があったこと、数人の医師が良心の呵責に悩んだことなど。人体実験は許されないことだが、こういう事件が起きてしまう当時の切迫した戦況もわかった。西部軍が引き起こした一連の事件の流れで考えるとまた理解が深まる。2023/01/18
うさを
3
「ああするよりほかに仕方がなかったのではないか」と、ある意味で逃げ道を用意した著者に、「それをいうてはいかんとです」と厳しく応じた関係者の言葉が鮮烈な印象を残す。遠藤周作『海と毒薬』からの流れで手に取った。小説を読んだ時と同様に、「生体解剖」という衝撃的な言葉からイメージされるような、特殊で猟奇的な事件で、遠い世界・時代の話なんだとして理解すべきではないと思った。大学であれ、科学・医学であれ、社会と無関係には存立しえない。そのなかで個々の研究者や医者がいかにあるべきかは、今まさに問われている事でもある。2014/08/09
-

- 電子書籍
- Gem Fragments オーブ 連…
-
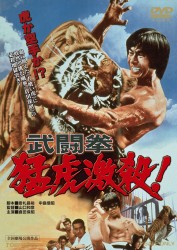
- DVD
- 武闘拳 猛虎激殺!