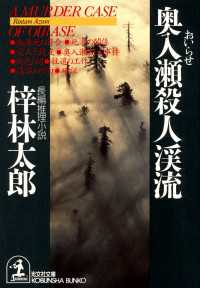内容説明
貧乏芸人、柳家小せんはある妓楼でひとりの女郎と出会う――。現在の落語を作り上げた破天荒な名人の生きざま、そして、彼を支える女房おときを、当時の風俗や文化を交えて描いてゆくノンフィクションノベル!
※本書は、2016年9月30日に配信を開始した単行本「小せんとおとき」をレーベル変更した作品です。(内容に変更はありませんのでご注意ください)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
gtn
13
明治16年生の小せんをCDで聴いたことがあるが、意外に甲高い声で、内容もあまり古さを感じさせない。江戸っ子というより東京人と評された由縁である。梅毒により腰が抜け、失明する前に、四代目桂文吾から「市助酒」を口伝されていたのは驚き。文吾も、名人と謳われながら酒毒のため足首を切り落とし不遇の人生を終えている。粋を気取りながら、その代償に翻弄された小せん。享年37。妻の無念はいかばかりか。2019/06/22
華形 満
6
久しぶりに素直に「良かった!」と読後感の良作だった。路地裏で三味線の音色が聴こえる様な江戸風情がすっかり無くなってしまい、こうした昔の”粋”とか”人情”は何処へ行ってしまったのか?私の世代でもぎりぎり瀬戸際だろうが「子別れ」やら「文七元結」など絶対に心底から離れない噺の数々。まるで本書そのものが落語のネタ帳の様に思えた。落語の文化は絶対に途絶えさせてはいけないとしみじみ思った。2016/11/29
菊蔵
4
数年前からあるきっかけで桂米朝さんの落語をCDで聴いたりしていたので(宿屋仇が滅茶苦茶好き!)こんな本があるのかーとちょっと興味を持って読んでみました。最近ではNHKでアテレコな「落語・ザ・ムービー」がなんともカッとんでいてホント面白かったし、落語って興味をもって見て聴けば、奥深く大した芸術品なのではないだろかと改めて思うに至る。(ハマるまでにはいっていませんが)本書は昔の落語家の生活などが見れて面白かったです。小せんの落語、聴いてみたかったなあ。2017/02/21
Miyoko Miura
1
何となく読んでいて、梅毒におかされて、失明する落語家小せんのことは50代とか60代だと思ってたら、享年36歳で一番ビックリした!!2017/01/17
kaz
0
当時の若手の噺家との交流の場面が少ないのは、テーマからしてやむを得ないか。巻末掲載の参考資料を見る限り、会話以外もかなりの部分はフィクションなのだろう。車夫の源蔵も実在したのだろうか。しかし、著者は雲右衛門の子孫だけに、書かれたもの意外に何か伝え聞いているのかもしれない。明治から大正の風情、小せんを支えるおときの姿等、事実であるかどうか関係なく、読み物として楽しむことができる一冊。 2016/12/30