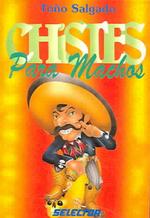内容説明
非戦のキリスト教知識人の最大のミッションとは何だったか? 内村鑑三門下の無教会キリスト教知識人,植民政策学者,東大総長,戦後啓蒙・戦後民主主義の象徴といった多面的な相貌と生涯を,預言者意識,「キリスト教ナショナリズム」,「キリスト教全体主義」,天皇観など,従来の矢内原像を刷新する新しい視点から描く.
目次
目 次
はじめに 預言者の肖像
第一章 無教会キリスト者の誕生──一九一〇年代
1 生い立ち
2 新渡戸稲造と内村鑑三
3 信仰、学問、交友
4 住友・別子銅山
第二章 植民政策学者の理想──一九二〇~三七年
1 東京帝国大学
2 植民政策学
3 帝国の理想──朝鮮と台湾
4 国際平和の理想──満洲と中国
第三章 東京帝大教授の伝道──一九三〇年代の危機と召命
1 帝大聖書研究会
2 マルクス主義とキリスト教
3 無教会伝道
4 二・二六事件と天皇
第四章 戦争の時代と非戦の預言者──一九三七~四五年
1 矢内原事件
2 無教会の雑誌・結社・ネットワーク
3 預言者的ナショナリズム
4 全体主義とキリスト教
第五章 キリスト教知識人の戦後啓蒙──一九四五~六一年
1 日本精神の転換
2 平和国家の理想
3 人間形成の教育
4 東大総長の伝道
おわりに 「神の国」の日本近代
あとがき
矢内原忠雄 略年譜
参考文献
写真出典
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ベイス
48
矢内原忠雄は畏れ多く近寄りがたい存在として私の脳裏にインプットされている。この著書は彼がなぜキリスト教無教会主義の信仰に入ったか、を明らかにするものではない。そうではなく、この信仰によって、どのように軍国主義と対峙したか、を分析する。興味深いのは、全体主義やナショナリズムという概念自体は、彼の思想と親和性があること。仕える相手が天皇か国家か、それとも父なる神なのか。大なる存在に従順に仕える特性をもつ日本人に、矢内原は希望を抱き続けた。いつか日本はキリスト教に導かれ救われる。しかしその希望は裏切られ続けた。2022/03/23
1.3manen
39
柏会は1909年に内村門下で結成された団体で、一高生と帝大生の十数人が参加していた。新渡戸稲造門下の読書会のメンバーであった(18頁)。矢内原は、新渡戸の下で植民政策講義を受けた他、アダム・スミスの『国富論』やエドウィン・セリグマンの『経済原論』を講読(26頁)。エレクシアとは「呼び出された音」を意味するギリシア語で、「教会」と訳され、無教会では「集会」と訳されることが多い。矢内原はこれを独占とすることに反対し、「信仰共同体」と訳語を充てている(97頁)。2017/12/21
浅香山三郎
18
昨年から、戦前・戦中の知識人たちのあり方に関する本を多く読むが、矢内原忠雄の戦争への対峙は独特である。無教会主義のキリスト教の伝道者の立場から、警鐘を打つといふのだから。 経済学者として、矢内原事件でしか記憶になかつた人物だつたけれども、かうした聖書原理主義的な思想と、植民地経済論、理論としてのマルクス主義への注目等、この頃の複雑な思潮を併せ持つた人物であつたことが興味深い。2018/01/20
さとうしん
11
戦中の「キリスト教知識人」としてのあり方を描くという本書の本筋からは外れるが、主に第二章で触れられている、矢内原忠雄と植民政策学との関わり、植民政策学が戦後に国際関係学・国際経済学へと発展したという話や、矢内原の殖民理論が近年グローバリゼーション論の先取りとして評価されているという点などを面白く読んだ。2017/10/10
amanon
10
この人は日本的キリスト教保守のいわば究極的なあり方を体現していたのでは?と思わされた。僕個人のあり方からすると受け入れがたい要素も散見されるが、皇室に崇敬を示しながらも、マルクスの著作にも通じ、戦前には軍部への批判を隠さなかったというそのバランス感覚と良識的なあり方には左右の立場を超えて尊敬に値する。ただ、その皇室崇拝が後にカルト的な一派を作り出す要因になったのでは?というのが気になるが。それからとりわけ痛ましかったのが、戦後社会への多大な期待が、失望に変わっていく過程。良心とは傷つくためにあるのか?2017/11/20