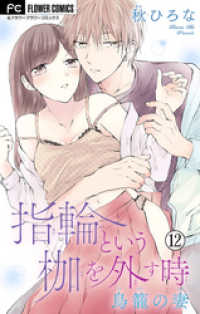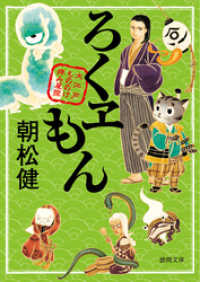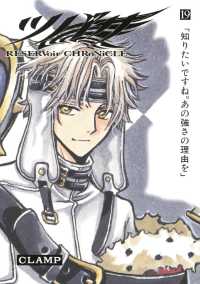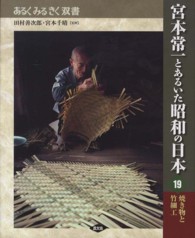内容説明
生命を維持するエネルギーの正体は何か、どんなメカニズムで作られ、どのように使われるか、その過程を紐解いていく1冊。高校生物でも登場する「ATP(アデノシン三リン酸)」がその鍵を握ります。本書前半では、ATPとそれを取り巻くしくみを、後半では、メカニズムを知ることでわかる、病気の原因について解説します。様々な病気に関わるATPやATPを合成する酵素。薬や診断法など医療への応用も期待されます。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
俊介
21
生化学って複雑な話が多くて理解するのに苦労するけど、本書はエネルギー代謝の話に的を絞っており、比較的分かりやすかった。「エネルギーの基軸通貨」とも形容されるATP。我々が食べ物などから摂取したエネルギーは、主にATPという物質に変換されなければエネルギーとして利用できないとこが、貿易決済におけるドルみたいなもの?だからそう言われるのだろう。本書によると、このエネルギーの変換過程は、発見当時、科学者でも理解するのに苦労したらしい。当初、何らかの化学物質を介在して変換されると考えられていた。2022/03/12
テイネハイランド
15
図書館本。こういう本を読むと世界中の研究者の努力により生物の中の微小器官の活動のメカニズムがわかってきたのを実感できて読んでいてワクワクします。これが数学や素粒子物理学だと読み手の理解力を超えたりしますが、バイオ系だとそこまで難解ではないのがいいですね。アメリカの名門MITで全学生が生物学の講義を履修するのも納得です。本書は細胞のエネルギー源となるATPの生成、およびATPを活用する器官の働きを解説した本ですが、目には見えないミクロの世界で風車やモノレールが動いているのが目に浮かぶようで楽しめました。2024/01/06
jjm
8
参考書では説明が不十分(個人的に自分の知りたい内容が書かれてない)である部分について、しっかり言及され、またとてもわかりやすく説明している良本。繰り返し読みたい。2020/08/03
arihero
7
グルコースが細胞に取り込まれエネルギーとなるATPが合成され、使用される仕組みが説明されています。化学とか苦手ですが、ATPが日々1500回もリサイクルされ、その70%がイオン輸送に使われているなど、食べた炭水化物がエネルギーとして使われているという意味がこれまでより深く理解できました。2023/07/30
うぃっくす
7
植物が光合成でつくってくれた糖をわたしたちが摂取して、それをグルコースとして細胞内に取り入れるとミトコンドリアでATPが合成される。ATPは汎用的にエネルギーを受け渡しするので生命活動に不可欠。そのATPを合成するためには複数のタンパク質が関わっている。それがファクター1でファクター1がATPを合成するようにするにはファクターオーが必要、と。このあたりまではなんとかついてこれた。けど二次構造、三次構造、立体構造とかでてきてお手上げ。興味深いテーマだけど難しかった。最近流行りの糖質オフってよくないのでは?2018/06/17