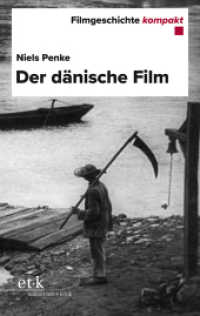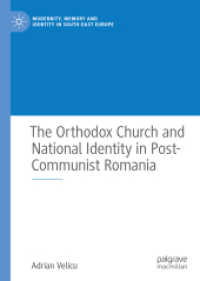内容説明
古代ローマに倣うように、ルネサンス宮廷に甦る仮設建築の凱旋門。それは入市式における君主の行列を迎える舞台、またメッセージを伝える大道具として機能し、さらに「生きた人間による絵画」の展示を加えて、大がかりな演劇的空間を作り出した。束の間の宮廷祝祭を彩った凱旋門と活人画は、その後、国民国家の記憶装置あるいは上流社会の娯楽としての道を歩みやがて明治日本にも伝来し独自の変容を遂げてゆく。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
スプリント
3
ハリボテの凱旋門で凱旋式を行ってその後に凱旋門を建造したことを本書で知りました。確かに、戻ってくるまでに建造できるわけないですよね。活人画は本書で初めて知りました。日本での活人画が裸産業につながっていたとは。2017/10/11
Bevel
0
活人画、さらに凱旋門で繋がる、非アカデミックな領域。なんと幸福な研究だろう!と同時に、京谷先生の知力と気品が溢れ出す。 p.287「読者の皆さまにも、どしどし活人画をしていただき、美意識を涵養したり、洒落のセンスを磨いたり、情操教育に役立てたりしてもらいたい。」2024/08/27
Yoshi
0
ルネサンスの張りぼての凱旋門と、その上で行われていた活人画の話。 すべての芸術は全く無用だ、とオスカーワイルドは言っているがそれを地で言っていてとても楽しめた。 ポッセッソなどの儀礼における張りぼて感と人間の欲を満たすための理由としての色々な用途を満たす凱旋門と活人画は歴史上残ってはいるがスポットライト自体はそこまであたっておらずそれをまるで灰汁のようにすくっている。2019/06/13
-

- 電子書籍
- Love Jossie 早瀬、先にイク…
-
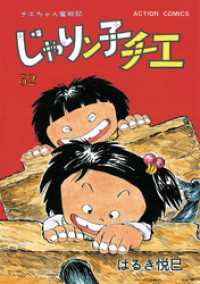
- 電子書籍
- じゃりン子チエ【新訂版】32 アクショ…