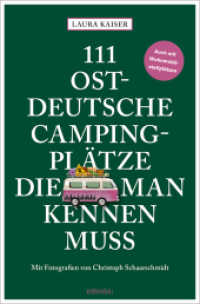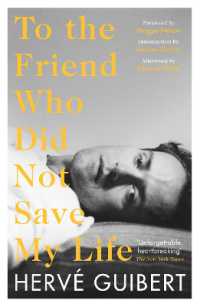内容説明
古代から中世にかけての錬金術は、ありふれた金属を黄金に変える術をはるかに超え、あらゆる物質の変容を研究する万能の学であった。錬金術師は、化学、金属学、薬学から、香料の精製や絵の具の調合まで、あらゆるジャンルの知と実学を探求した。例えば「東洋の神秘」であった磁器の製法を解明したのも、18世紀のドイツ人錬金術師であった。本書で著者は古代、中世、近代の錬金術師の秘密の処方箋を明らかにし、万能の学の復活を提唱する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
銀獅子王の憂鬱
3
非常に興味深い本。錬金術は化学を精神世界で捉えた世界だと理解できた。三元素である「精神」「魂」「肉体」が抽象化された宇宙、化学と「言語」(ロゴス)レベルで融合し、錬金術という落とし子が生まれた。ただし化学の発達により錬金術は忘れ去れ、ロゴスがけが残ったと解釈しました。また本書は錬金術の入門書としての位置づけもあり、それらの解説を読むのも面白い。2010/12/12
幽谷響子
2
ハードカバー挿絵付き活字本 『化学の結婚』とか、他の思想匂わせてくるのいいよね2025/12/15
さしとおう
2
錬金術入門書。錬金術師は蒸留がお好みのようで。2009/06/20
Kyohei Matsumoto
1
錬金術の考え方の基本を知るにはよいかと。プリママテリカ、硫黄、水銀、塩の3分節的考え方、地水風火の4分節的考え方、惑星との対応、物質の捉え方、それから具体的な手技も書いてあった。もちろんその実験を行うのは現代ではかなり難しいが、普通に書いてあったので実験室とかでやろうと思えばできると思われる。個人的にものすごく学んだのは惑星の記号が太陽🌞と月🌙四大元素を示す+の三つの組み合わせで成り立っているということ。そして、水銀(Hg)と哲学的水銀という全く違うものが出てきた。分けて考えるらしい。2022/10/10
雫
1
錬金術って聞くとどうしてもゲーム・マンガにあるようなファンタジー要素を感じるけれど、根本的には金属を火で加工するとかフラスコで蒸留するとか現代の化学の素みたいな感じなんですね。ただ現代みたいに物質先行で捉えるんじゃなく、そのものに宿る魂の力だったり生命力の観念を重視してるという点では現代とは観点が違うなと思った。昔は占星術が今よりもっと重視されてたりしてたこともあるし、その時代ごとの学問なんだろうなって感じ。あと本に使われているイラストが雰囲気すごく合っててよかった。2021/01/01
-

- 電子書籍
- 土竜の唄(88) ヤングサンデーコミッ…