- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
昭和20年4月1日。少年・矢島喜八郎、のちの作家・西村京太郎は、エリート将校養成機関「東京陸軍幼年学校」に入学した。8月15日の敗戦までの、短くも濃密な4か月半。「天皇の軍隊」の実像に戸惑い、同級生の遺体を燃やしながら死生観を培い、「本土決戦で楯となれ」という命令に覚悟を決めた――。戦時下の少年は何を見て、何を悟ったのか。そして、戦後の混乱をどのように生き抜いて作家となったのか。本書は、自身の来歴について、著者が初めて書き下ろした自伝的ノンフィクション。いまこそ傾聴したい、戦中派の貴重な証言である。【目次】第一章 十五歳の戦争/第二章 私の戦後――特に昭和二十年(前半は戦争、後半は平和だった時代)/第三章 日本人は戦争に向いていない/主要参考文献
目次
第一章 十五歳の戦争
第二章 私の戦後――特に昭和二十年(前半は戦争、後半は平和だった時代)
第三章 日本人は戦争に向いていない
主要参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
96
ミステリー作家西村京太郎氏が体験した戦争について描かれている。戦争のことを語るということは戦争を体験したものでないと書けないと思う。過去の戦争について過ちや反省という言葉が使われるがそれは体験していないから使えるのかもしれない。鴻上尚史の本で読んだ特攻の方もいろんな体験をしたにも関わらず当時のことをあまり語ろうとしなかったという。戦争に対して饒舌に語れば語るほど無責任かもしれない。個人がとにかく戦争という愚かな行為を考えることがいちばん大切だと感じた。2018/01/14
あすなろ@no book, no life.
76
昭和20年、私は陸軍幼年学校にいた。陸軍幼年学校とは?という点から手にした本。陸軍幼年学校卒は、自ら陸軍エリートを意識し、昭和維新中核を意識したという。結論から言うと、もっとここを書き込んで頂きたかった。少し焦点散漫な西村京太郎二次大戦論。しかし、桶狭間の戦を好む陸軍・戦闘機を二種持った陸軍と海軍・国内戦と国際戦の意識相違・日本の軍人は死を生の上に置く議論・永田鉄山の考え等興味深く読了。いろいろ書き連ねの集積本。総称して、西村論では、日本人は平和に向いているのである、と結んでいる。2017/09/03
Willie the Wildcat
64
淡々と語る半生に垣間見る大戦を挟んだ”変化”。衣食住に教育・仕事。踏まえた大戦への考察。『戦陣訓の罪』は、現代にも繋がる悪癖という感。物理・心理の両面での”縛り”。言うまでもなく、著者自身も戦前・戦中に感じた矛盾も呪縛下の話。一方、著者出世作にも繋がる”ブルトレ”の件は、”縛り”への対照であり皮肉と解釈。先人の残す様々な形での教訓を、もれなく活かしていくのは当然の義務ですね。2017/09/29
rico
43
西村京太郎さんと言えば鉄道ミステリーのイメージだけど、陸軍士官学校出身だったんですね。士官学校時代の話はわりと短くて戦後の記述が長め。最前線に出る前に終戦を迎えたこともあって、戦いの悲惨さよりも、軍人や教師、政治家たちに対する批判的考察が中心。少し物足りない感じもするけど、あの戦争について直接語り得る最後の世代の意地を感じる。それにしても、権力者が責任をとらないとか、精神論が跋扈して冷静な分析ができないとか、忖度で事が動くとか・・・この国は情けないぐらい変わっていない。2018/08/16
slider129
38
先の大戦をテーマにした本は数多くあるが、史実を知識として受け取る事は出来ても、当時を生きた人が経験したであろう、時代が持っていた空気や当時の感情まではなかなか伝えてくれない。あの時代、亡き父は南方へ出征していたが当時のことは黙して語らず、また亡き母は疎開していたので都会の空襲の地獄は経験していない。そんな戦争経験者がこの数年でいなくなるであろう今の時代に、語る事が出来る語り部の言葉や、文章で残す事が出来る西村氏のような作家が書き残してくれる本書のような存在がとても貴重に感じる。いい本を書いて下さった。 2017/08/31
-

- 電子書籍
- オキナワグラフ2024年09月号
-
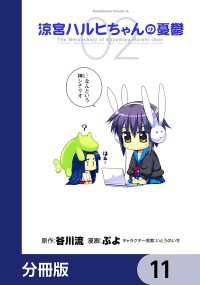
- 電子書籍
- 涼宮ハルヒちゃんの憂鬱【分冊版】 11…
-
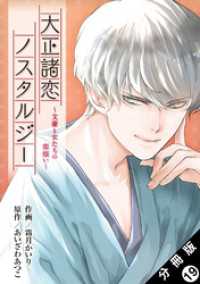
- 電子書籍
- 大正諸恋ノスタルジー~文豪と女たちの恋…
-
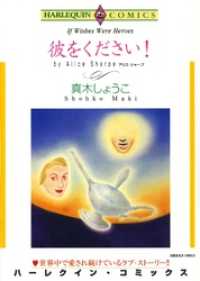
- 電子書籍
- 彼をください!【分冊】 8巻 ハーレク…
-
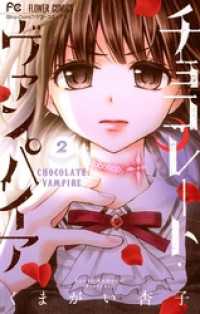
- 電子書籍
- チョコレート・ヴァンパイア(2) フラ…




