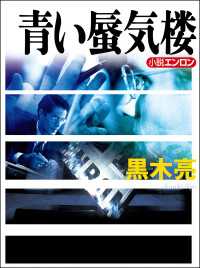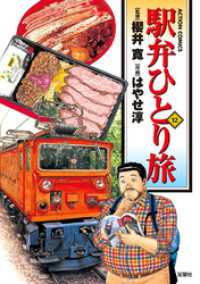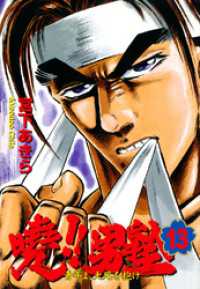内容説明
人間社会の構築やコミュニケーション行為における意思や情報の伝達と秘匿の必要性から発生し、時代や社会の変遷とともに発展、進化しつづけた暗号。そこには数千年におよぶ人類の叡智がこめられている--。世界や日本のさまざまな暗号の実際と理論、そして歴史的な変遷を、豊富な具体的な例を掲げ平易かつ簡潔に網羅した〈日本暗号学〉不朽の古典!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
BLACK無糖好き
17
原本は1971年刊と古いが、暗号の発展過程を豊富な実例を元に解説した資料的価値のある古典作品。◆文字の変換、配列の変換、鍵語と鍵語による換字表の作成、鍵語から鍵乱字(鍵乱数)へ、乱数性の検定、多表式の機械化、暗号機の規約、機械暗号の解読。夫々よくこんな事考えつくなと感心するばかり、いや、殆ど難解すぎてついて行けないのが正直な所、近年は、やれビッグデータだAIだと喧しいが、本書を読むと人類の叡智の奥深さを見せられた気分になる。安易に機械に頼らずにどこまで己の頭脳を振り絞れるか、試されているようだ。2017/09/05
Akito Yoshiue
8
個々のエピソードが非常に面白い。漢字と暗号の章が特によかった。2017/09/05
spica015
6
原本が古いので現行の情報技術には対応していないものの、書物を繙けば古代より暗号が用いられてきたことがよく解り、『日本書記』や和歌に暗号が登場していることに興味を覚えた。暗号が生まれた背景を知るのであれば『暗号解読』の方に軍配があがるが、こちらは漢字や隠語についても触れられており、より親しみやすい内容になっている。乱数表がどーんと掲載されていたりと、本格的な内容に面食らいつつ、掻い摘まんで読むだけでも面白い。2017/09/04
roughfractus02
4
交わされる言葉は、それを知らない者にとっての暗号である。著者は言葉自身を「暗号らしくない暗号」と呼ぶ。この点で漢字という大陸からの渡来文字に訓読を施すことは暗号を解読する行為である。その古さ(1971年刊)にかかわらず、IT社会において「暗号らしい暗号」がを扱うこの類いの本が日々更新される速度に遅れる点に逆行するような本書の魅力は、フレイザー『金枝篇』の未開社会での名づけ、『古今和歌集』の折句、フリーメーソンの特殊記号、探偵小説の暗号等の解読を、人事、外交の暗号と同列に人間の知の営為として扱う点にある。2018/01/08
TOMOKO DOI
3
(図書館)読んでて面白かったのだけど、仕組みがわかってしまったらもはや暗号ではない…とおもった、、2017/09/03