内容説明
人口46万人都市に観光客800万人!なぜそんなに人気?金沢21世紀美術館特任館長が見た、聞いた、本当の金沢。情緒あふれるまち並み、穏やかな古都?いえいえ、とんでもない!伝統対現代のバトル、旦那衆の遊びっぷり、東京を捨て金沢目指す若者たち。実はそうぞうしく盛り上がっているのです。よそ者が10年住んでわかった、本当の魅力。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
野のこ
46
21美の前館長の秋元さん。21美が出来てからアートが身近になりました。伝統工芸と現代アートの出会いは魅力的で、高校の友人がまさに陶芸のアートを作っています。彼女の白くて紙が折り重なったような造形美、素敵なんです。金沢人の「腹が読めないやりとり」 お食事のお誘いで最後の最後に「そういえば~」と今回誘った目的をさりげなく言う。私はやらないけど経験ありです。市の美術館なので前市長との交流が深かくたくさん登場でした。金沢の驚きと共に前市長のパワフルな人柄も知れました。二年前に隣の市に移ったので最近はイオン漬けです2018/01/13
クラムボン
19
著者の秋山さんは2007年から10年間、金沢21世紀美術館の館長だった方です。今では市民にも観光スポットとしても大人気のようですが、当初は伝統工芸の町金沢とは正反対の現代美術館への反発が大きかった。特に地元の工芸家が気分を害した。日本の公共美術館は伝統的に「日展・県展」など地元作家の作品の展示場として始まったが、それをアッサリ切り捨てたからだ。当時の山出市長の考え方が圧倒的に大きかった。よそ者の著者が苦労しながらも地元に溶け込み、金沢の町を称賛するに至る過程が語られています。ただ少し褒め過ぎですが…。2022/01/03
くるみみ
16
著者は金沢21世紀美術館の2代目館長でその前は直島アートプロジェクトの立ち上げスタッフでもあり教授でもあるアート界の方。タイトルからして地場産業や地縁に基づく話なのかなと思ってたけれど、第1章「金沢21世紀美術館の嫌われぶり」から白眉。現代アート美術館と伝統がある工芸との取り合わせは日展をイメージしていた工芸畑の方たちや市民には当時は大きな違和感しかないだろう。現在は現代アートと工芸の相性の良さは周知されているけれど。第4章「城下町のプライドにおどろく」のような話も読めて、更に金沢に興味が湧く良書だった。2023/11/19
さっちん@顔面書評
8
ああ、やっぱり金沢って魅力的なマチなんだなと思いました。 色々な都合が重なって3年ほど前に4ヶ月くらい住んでいたことがありましたが、その時のことを思い出しました。 まだ金沢の魅力の入り口しか理解できていなかったと思うと少し残念な気持ちと、もう一度住みたいという気持ちが出てきました。 目指せ2拠点生活! 東京生れ東京育ちの外部から金沢にやってきて21世紀美術館の館長をやられた方が書かれているので、金沢を外と中、両面から見られてる視点が面白いです。金沢を理解するうえでオススメの1冊。2023/05/26
yyrn
8
ハイハイ、金沢はすごいですね。敵わないですね。きっと金沢に住んでいる人たちはみんな幸せなんでしょうね。それを自慢したいんでしょうね、と皮肉を言いたくなるような本だった。地域を輝かせるために必要なこととして紹介している著者が関与した取り組みや主張はよくわかるし、大変に素晴らしいと思うが、どうも感情が拒否反応を示すのでほめる言葉が素直に出てこない。嫉妬しているのかな?やりたくてもできないから。イヤイヤそれよりも私が現代美術の良さをサッパリ理解できないせいかもしれない。一体どこがイイのかと。2017/07/27
-
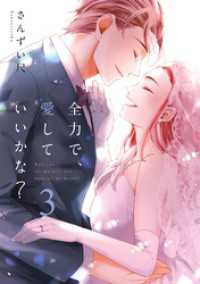
- 電子書籍
- 全力で、愛していいかな?【電子単行本】…
-

- 電子書籍
- 高分子機能材料シリーズ 9 医療機能材料
-
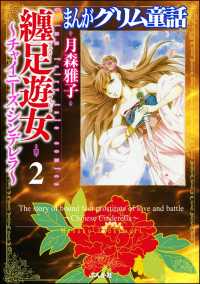
- 電子書籍
- まんがグリム童話 纏足遊女~チャイニー…
-

- 電子書籍
- 妄想ぺんしる フラワーコミックス
-
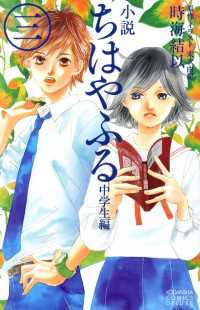
- 電子書籍
- 小説 ちはやふる 中学生編(3) KC…




