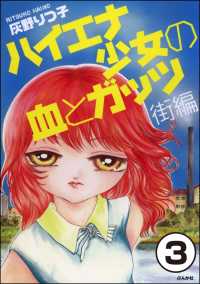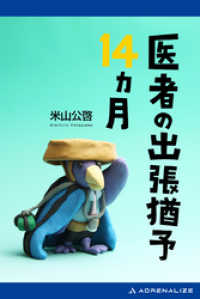内容説明
「皆さんは国語の授業が好きでしたか?」
帰国子女という言葉すらなかった時代。
コモリくんは書き言葉で話す、周りとちょっと違う小学生。そのためにみんなと“仲間”になり切れず、国語(特に作文!)が大嫌いになったコモリくん。
そんな彼は日本語と格闘し、海外で日本文学を教える側になり、ついには日本を代表する漱石研究者にまでなってしまう。
米原万里氏ら多くの作家も笑賛した、自伝的エッセイの名著。
言葉という不思議なものを巡る冒険の書。
解説は『日本語が亡びるとき』の水村美苗氏。
※本書は二〇〇〇年四月、大修館書店より刊行された『小森陽一、ニホン語に出会う』を改題し、加筆・修正をしたものが底本です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
penguin-blue
37
チェコのロシア語学校で学んだ小学校低学年時代。海外の学校で日本語以外を所謂「国語」として学んだ経験がある人の多くは日本に帰ってからの国語の授業に戸惑いを覚えるらしい。作者はずっとその違和感を持ち続けたまま成長するが、すごいと思うのは結局その日本の文学を教える職業についたこと。こういう迷いを経験した人に教わることは幸せなことなのではないか。恐らく通常の国語の授業以上に真正面から日本の近代文学を読み込み、向き合おうとする授業が興味深い。読んで日本には「みんなが共通でわかる文学」がないことを痛感する。2018/02/04
navyblue
21
6月、小森先生が担当された夏目漱石を読む講座が大変面白かった。すっかり魅了され、この本を手に取った。なんとあの米原万里さんと同じチェコのロシア語学校におられたとは!帰国子女として、「国語」と「日本語」の狭間で苦労された様子が興味深く書かれている。日本語を教えることについても改めて考えるきっかけになった。小学校、中学校、高校の国語のライブ授業のページは、活字でありながらその場で講義を受けているような臨場感が味わえる。そして解説はあの「水村美苗」さんだ。素晴らしすぎる。「こころ」読み返そうかな。2017/08/23
たま
20
「井上ひさしを読む」を読んで編者の小森さんが帰国子「男」で外国語と日本語の習得について思うところありと知り、この本を読みました。日本に住んでいると、親が日本人なら自然と日本語が話せるはずとか、外国で育てば自然と外国語が話せるはずとか、そんな通念が蔓延しているのだけど、それに対する異議申し立てとして読んだ。それにしてもこの通念は本当に強くて、普通の日本語で自分の考えを表現する訓練をやらないし、その結果そういうことができる政治家もいない。なんとか変えていかないと、と思う。2020/08/19
ドシル
10
日本で生まれ、その後チェコスロバキアのソビエト学校で学んでいた著者が、自身の日本語の習得過程を俯瞰し、振り返っている前半。 諸事情により、大嫌いな国語の教員になったり、日本近代文学を専門とするようになるから人生は不思議だ。 小学校や中学校への「道場破り」のやり方も興味深い。 私の母語は日本語だから、あまり運用できるようになった過程は意識したことはない。 帰国子女の学習言語獲得や異文化でのカルチャーショックはなんだか、ろう者やコーダから聞いた話との共通点が多いように思った。2017/09/23
はなびや
6
『小森陽一、ニホン語に出会う』を以前読んだ記憶があり、文庫になったこの本を読んでみた。チェコスロバキアでのロシア語教育を経て、日本に帰国してからの日本語教育。言葉が話せることと、その国の国語教育と文化に慣れるまでの葛藤。多感な時期に、異なる文化の言語を取得し、日本人でありながら、しばらくはロシア語で物を考え、日本語に自分で翻訳をして考えるという、バイリンガルと簡単に言うが簡単ではない。国語が最も嫌いな科目であるにも関わらず、近代文学の研究者という不可解な経歴の謎が明かされる。在日外国人の教育を考える上でも2020/03/19