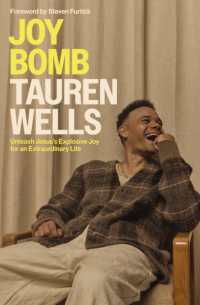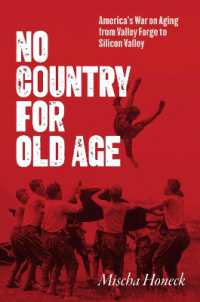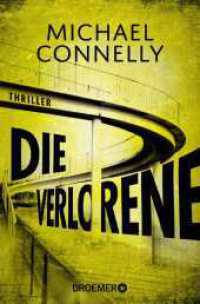内容説明
▼キリスト教を背景とした、キリスト教の内部の思想である「中世哲学=スコラ哲学」を、「感覚」の次元でとらえる。
▼ワインの生産、肉食やパン食の普及など、市民生活に根差した文化や習慣の観点からスコラ哲学を考察することで、西洋中世の生き生きとした側面を明らかにする。
▼すべてのひとに共通する普遍性の次元である「五感」。味覚、触覚などの身近な感覚をとおして、「感じる」スコラ哲学をかんがえる、画期的な中世哲学入門書。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さえきかずひこ
5
ワインについての記述がとても面白かった。そして、キリスト教神秘主義へ…。難解ではあるが、キリスト教神秘主義の存在の扱い方は、20世紀の実存の流れに連なる…というか源流なのかな。変わった本です。うまく感想がまとまらないですが、こみ入りながらもふわふわした感じがある読後感。2017/01/19
もっち
5
めちゃおもしろい。味覚の哲学について考えていたので、とてもいい内容2016/07/08
♨️
3
反復を通じて「私」として現実化されるハビトゥスが身体性を通じて形成されてゆく(生きている限り、されつづける)ものならば、概念以上にすぐれて身体と関係するような感覚・感情といった問題が重要となる。哲学がその次元においてなされる明晰性などの「思惟可能性」に対する「表象可能性」という問題を考えるために、中世哲学などでの味覚や「霊的酩酊」という比喩が検討されるほか、受動(=情念)は必ずしも不自由ではないというスコトゥスの自由意志論(それはハビトゥスの基礎だろう)、神秘主義の神についての経験を語る=表象することの2023/02/07
toiwata
2
キリスト教のソースプログラムはラテン語の感。<<ほんの一歩を進むために人生を費やした人間がいても、それも学問の姿だと思います。>>p.3 <<中世のスコラ哲学は、カトリック神学の牙城です。>>p.22 <<教会制度というものはきわめてフィクショナルなものです。>>p.742017/05/21
ざっきい
2
中世スコラ哲学極上の入門書、との帯に惹かれ読んだ本。実際は入門書ではなく、ちょっとこの辺りの話を(「知性」面から)聞き齧っている人に対し、「知恵」面の話をするといった内容。やや散漫だが、中世スコラ哲学の雰囲気を味わえる良書と思う。自然的意志と自由意志を分けたり、神への罪と世俗の罪を分けたり、適度な快楽を指示したりと、概念を楽しんでいる様子がわかる。また、著者のいう「もしAであるならBではないか」という文脈で「Aであるなら」自体が飲み込めないことが多い気がした。2017/02/19
-
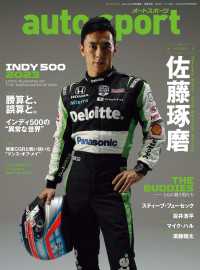
- 電子書籍
- AUTOSPORT特別編集 佐藤琢磨 …