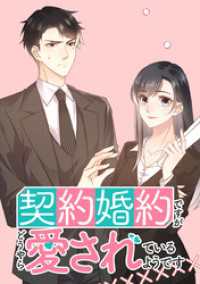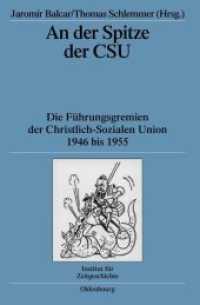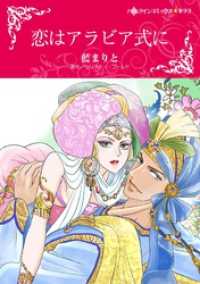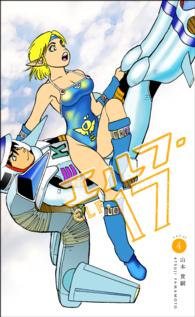内容説明
1978年生まれの筆者の周囲にあったのは、茫漠たる郊外――ニュータウンだった。
その出発点から、戦後思想とはどのように映るのか?
大東亜戦争、象徴天皇、三島由紀夫、小林秀雄、福田恆存、柄谷行人、中上健次、
坂口安吾、あるいはロレンス、ピケティ……。思索を深めるにつれ、あらわれて
きたのは「政治と文学」という問題だった。
本書は、必ずしも「戦後批判」を志向していない、端的に「戦後よ、さよなら」と言うものだと考えてもらいたい、と筆者は言う。
「いずれにしろ、私は「政治と文学」のけじめを曖昧にしながら、いつかその両者が一致するだろうことを夢見るような「戦後」的な言葉については何の興味もないことだけは断っておきたい。私の描きたかったのは、人間の可能性ではなく、必然性であり、人間の自由ではなく事実だった。」 (あとがきより)
いま文芸、論壇界で注目を集める気鋭の批評家が戦後思想に新たな問題を提起する画期的論考!
【目次】
I部―政治と文学
郊外論/故郷論―「虚構の時代」の後に
三島由紀夫の宿命―〈文学―天皇―自決〉の連関について
「象徴天皇」の孤独
宿命としての大東亜戦争
「戦後」よ、さようなら
II部―文学と政治
中上健次と私
小説の運命
柄谷行人試論―〈単独者=文学〉の場所をめぐって
福田恆存とシェイクスピア、その紐帯
坂口安吾の「いたわり」
III部―幸福について
「落ち着き」の在処
ロレンスとピケティ―交換可能なものに抗して
小林秀雄の〈批評=学問〉論
落語の笑い―春風亭一之輔の方へ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ドクターK(仮)
3
「政治と文学」という、答えのない(ように見える)テーマに真正面から取り組んだ評論集。三島由紀夫、福田恆存、小林秀雄、柄谷行人など、名だたる文学者たちの言葉を丹念に読み解くことで、「政治」と「文学」それぞれの輪郭とその関係が徐々に浮かび上がってくる。前者は「有用性を基準とした優/劣の線引きによって人間の生活を一般化し、規則化する営み」であり、後者は「有用性だけでは生きていけない人間の一回的な生に寄り添い、それと共振する営み」(p.282)であるとした上で、その接点を見極める努力が求められていると著者は言う。2017/07/12
Akkikky
1
注目の若手保守論客の著書で個人的にはアカデミックな観点で最も故西部邁氏の思想を引継いでいらっしゃると感じる。私自身戦後レジームが現代日本衰弱の根源と考えており、『反戦後論』と言う書名はそそるもの。内容はハイデガーや福田恆存などの思想的視座が予備知識としてないと難解な部分もある。しかし著者が述べたいことは、所謂「理想と現実」の間に如何に共通項、妥結点を見つけ生きて行くのかと言うことに尽きると思う。現実の有用性に傾きすぎている現代にあっては難多しだが、理想を見つめつつ現実を漸進する気概をいただけた。2019/04/23
shouyi.
1
政治と文学など、おもしろい評論集だった。途中難しくて投げてしまいたくもなかったが、投げなくて良かった。文学が現在どのような位置にあるのかがよくわかった。2018/03/19
静かな生活
0
REVIEW SCORES 70/1002024/06/05