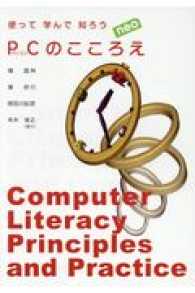内容説明
この村に、男は都会からやって来た。女は都会から舞い戻った。若い二人を結びつけたのは、異様なヒジリの風習だった。男女の愛の生成を土俗的な集団幻想を背景に描出した野心作『聖(ひじり)』と、その続編で、両者が東京で生活を構えてからの営みを多面的に追求した『栖(すみか)』(日本文学大賞受賞)を同時収録。現代の極北を行く著者の斬新で緻密な才能の精華。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
相生
10
『聖』は〈外〉から村の共同体へ、もっと詳しく言えば村の共同体の記憶、慣習の中へ引き込まれる物語で、その後日談『栖』は〈外〉に出た人間の内部から共同体の記憶、慣習が引きずり出される物語、というふうに読めた。個人的には『栖』の方が印象が濃くて(というかページ数的に1対3くらいあるし)、佐枝の気の振れ方とその過程の描き方がとってもねっとりとしていてとても好み。世帯を持つことの期待が佐枝を狂わせ、そのヒビのような所から村の共同体の記憶としての振る舞いが滲むように出てくることが興味深い。2015/11/25
yumiha
5
死はケガレ。一族があるいは共同体がケガレから逃れるためのサエモンヒジリ。サエモンヒジリを時に敬い時に侮る村人たちの態度に、死への視線が見える『聖』。そして、その村で生まれ育った佐枝とサエモンヒジリになり損ねた?岩崎の都会での凄惨な暮らしを綴る『栖』。佐枝がだんだん精神を病んでいけばいくほど、その緻密な描写に、わたしまで重たく鈍く狂いそうになる気分を味わった。2010/10/22
Mark.jr
3
とある山奥にやって来た男が、そこに伝わる奇妙な風習によって、女性と関わりを持つ「聖」。著者の本の中でも、民俗学的な装飾が目立つ作品で、全体に漂う不条理感といい、安部公房の「砂の女」をちょっと思い出しました。もう一つ、「聖」の男女が東京に出て所帯を持つ生活を描いた「栖」は、前者と比べて幻想的要素がほぼ無い分、より現実の重みや手触りのようなものがダイレクトに伝わってくる作品になっていると思います。2022/01/21
夜明けのナッキー
2
都会人の主人公が村のサエモンヒジリとしての役割を担わされ小屋に住まわせられる『聖』。過去のヒジリにまつわる言い伝えによってしだいに色濃く甦ってくる風習の世界は現代社会とは別の、主人公と佐枝の家のあいだに出現したもう一つの世界がうかがえる。『栖』は、村の共同体から都会の一室、そして岩崎と同棲してからは自分の深部へと次第に佐枝の栖(すみか)が内へ内へと狭まっていき、そして収まりきれなくなった内なる物が狂気となり不穏な空気を生み出していく。他人の侵入を拒む領域のようなもの、それが侵されたとき何かが壊れていく。2011/12/10
Bevel
2
身体が欲しいのか、心が欲しいのか、それとも両方欲しいのか。そんなこと考えてもしょうがないと思うんです。ただ受け入れ続けることだけで、何かが見えてくるのかもしれません。けれど、そういったことでもないんです。ただ、どうしようもない、って俯いてしまう。意識が同じところを無造作にいったりきたりするような感触を的確に表現する文体があって、それは彼の小説において絶対崩れない。たまにひょっこり顔を出す若さも、すべて飲み込まれていくんです。2009/11/12