内容説明
カストルプ青年は、日常世界から隔離され病気と死に支配された“魔の山”の療養所で、精神と本能的生命、秩序と混沌、合理と非合理などの対立する諸相を経験し、やがて“愛と善意”のヒューマニズムを予感しながら第一次大戦に参戦してゆく。思想・哲学・宗教・政治などを論じ、人間存在の根源を追究した「魔の山」は「ファウスト」「ツァラトストラ」と並ぶ二十世紀文学屈指の名作である。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
116
読み終えるのに苦労した。面白くないわけではない。主人公たちが、突き詰めて話をする内容が息苦しく、彼らがどこへ行くのかが不安に思えた。殺人犯には極刑をもってすべきか。フリーメーソンとは結局何か? 男女の関係とは? そんなことをひたすら突き詰めて、時に喧嘩しながら、さらには決闘にまで発展するほど議論し、話を続ける。しかし、それが行われる場所は結局サナトリウムなのだ。彼らは時間を持て余し、甘やかされた生活をおくり、病気をかかえてはいても現実社会というものを結局は知らない。さて、彼らの議論の行く先は…。2015/03/24
アキ
98
NHK100分de名著で取り上げられてから2か月かけて読み終えた。まるで現実の世界とは異なる療養所の魔の世界に迷い込んだような強烈な読書体験でした。今から100年前に完成まで12年を費やして書かれた本書は、当時のヨーロッパの思想的混乱を、フリーメイソンのイタリア人セテムブリーニとイエズス会士でユダヤ人のナフタとの会話で表しているようであった。7年間にわたるハンス・カストルプの「ベルクホーフ」での生活を、地上の生活とは異なる時間の感覚、死を常に意識した病気、ショーシャ夫人への恋慕と関係を堪能させる教養小説。2024/07/20
扉のこちら側
88
初読。2015年1123冊め。【71ー2/G1000】まず「終わり」の文字がなければここで完結したとは思えない終わり方。訳者も解説で書かれているが、第六章の「雪」で終わった方が、物語としての締まりはよいだろう。作中で突入した第一次世界大戦が、物語に幕を引いたように思う。下界=人間世界を、魔の山から俯瞰する物語。【第6回G1000チャレンジ】【第20回月曜から読書会】2015/11/09
のっち♬
79
本書は時間の相対性、哲学、愛、病の認識と医学、生と死、宗教、音楽と文学、言語といった様々なテーマを深く掘り下げており、死の病を患い、常に死を意識する人たちを著者は見事に描き上げている。中でも、セテムブリーニと新たに現れた論敵の虚無主義者ナフタのどこか不毛な思想のぶつかり合いや実業家ペーペルコンの登場は下巻のハイライトだろう。今となっては流石に時代を感じないでもないが、これも大戦前のヨーロッパの縮図か。着想から出版まで12年にも渡って膨れ上がった力作。読後の疲労感と達成感が独特の余韻を残す。覚悟のいる登山。2019/12/24
香取奈保佐
64
シナリオには結局山らしい山もなく、長い小説だった。主人公のハンス・カストルプは結局七年間も「魔の山」に居続けた。彼はその間にさまざまなことを見聞きし体験するのであるが、実社会に足を置かない彼の「根無し草」な経験にどれほど価値があるかは疑わしい。つまり、非常に意義を見出すのが難しい小説だと思った。形而上の話についての箇所は、確かに出来はいいのかもしれないが。「旅行者は山の頂上で一息つくのを楽しむが、いつまでも休んでいろといわれたら、幸福でいられようか?」というスタンダール『赤と黒』の一節を思い出した。2015/04/04
-
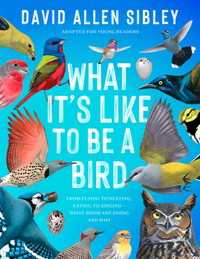
- 洋書電子書籍
- What It's Like to B…
-
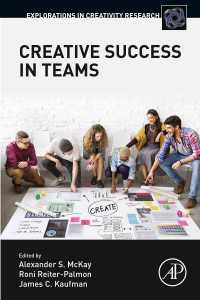
- 洋書電子書籍
-
チームの成功のための創造性
Cr…







