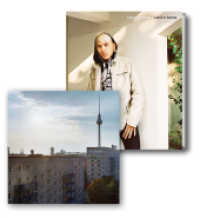内容説明
戦前社会が「ただまっ暗だったというのは間違いでなければうそである」(山本夏彦)。戦争が間近に迫っていても、庶民はその日その日をやりくりして生活する。サラリーマンの月給、家賃の相場、学歴と出世の関係、さらには女性の服装と社会的ステータスの関係まで──。豊富な資料と具体的なイメージを通して、戦前日本の「普通の人」の生活感覚を明らかにする。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Willie the Wildcat
58
より良い生活を求める心は、いつの時代も不変。社会が生み出す格差・差別も、悲しき現実であり不変。失業保険や公的年金などの社会保障はなく、今以上に格差社会とも言える世の中では、大戦に向かう世相形成も論理的。但し、戦争責任は誰も念頭にはなく、唯々日々の生活向上だけではなかろうか。衣食住の変化の過渡期でもあり、否応なく変化に適用していく過程が、時に羨ましく時に寂しくも感じる。たとえ貧しくとも、長屋や質屋など人々の距離感が近いよなぁ。2017/05/08
リキヨシオ
34
終戦後における人々の復興へのスローガンは「昭和八年に帰ろう」だったらしい。平和な戦前日本で最も経済が安定した「昭和ヒトケタ」の時期のサラリーマンの平均月給は100円だった。月給100円のサラリーマンの生活から戦争へと向かう不穏な戦前の政治家や軍人ではない普通の人々の生活が描かれる。現代と月給100円時代における物価の違いは約2000倍…当時を知って意外な点もあったけど、現代と共通する点も多かった…どの時代にも今の若者はダメだ議論はあり経済格差はあり学歴社会もあり政治家への不満や閉塞感の打開への渇望がある。2017/06/01
サーフ
16
戦前の日本と現代の日本における共通点の多さに驚く。物価 や労働環境などは大きな差はあるが、生活に関わりがある部分は現代にも共通する点がある。早慶戦で町を暴れ倒す若者は今のハロウィンにも通ずるし、学力低下を憂う識者は今だっている。ただ現代よりも圧倒的に学力至上主義な点など今のほうが生きやすいのかなと思う。また戦前というと特高警察など閉鎖的で暗いイメージがあったがこの本に書かれているものはそのような暗いイメージは全く無い。2018/10/30
rico
13
月給だけでなく、着物から家賃、外食やお酒など色々なものの「値段」が次々と出てくる。ただの数字なんだけど、「2000倍」にして今の価値に換算するだけで、一般の人たちの暮らしがリアルに見えてきて楽しい。大学の勉強など役に立たない、若者はもっと海外に出るべきと憂えてみせる識者とか、バブル期の武勇伝を語って、若い人からうっとおしがられるおじさんとか…あまりに変わってなくて、笑えてしまう。でもそれだけに最後の1行が怖い。「やはり戦争はいきなりやってくる。だまっているとやってくる。」2017/04/13
yuzyuz_k
10
読み終わって思う事は、人間って中々成長しない生き物なんだと言う事です。(自戒) 学歴、成果(実力)主義、賃貸と持ち家、学力低下、援助交際、バブル、男女の給与格差。 の事が話題になっています。 2006年に書かれた本ですが、ネット時代の現代でも当てはまりま過ぎて、笑ってしまいました。 別で昭和30年代の雑誌を2年分程度、流し読みした事もあるんですが、それも同じ感じだった事も思い出しました。 2018/03/18
-

- 電子書籍
- 夜明けを焦がす星々: 1【電子限定描き…
-
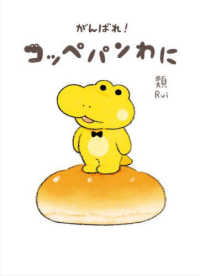
- 和書
- がんばれ!コッペパンわに