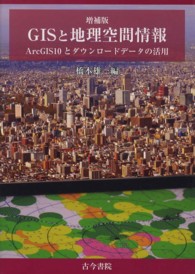- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
<本と日本史>は各時代を代表する「本」のあり方から当時の文化や社会の姿を考え、その時代における世界観・価値観の成立を考察する歴史シリーズである。本書が扱うのは、宣教師と『太平記』の意外な関係だ。南北朝~室町期の武士の生きざまを描いた『太平記』は、戦国時代最大のベストセラーであり、数々の武将たちに愛好されていた。だからこそ、宣教師もこの作品を「日本を知るための最高の教科書」とみなして、必死に読み解こうとしたのであった。『太平記』と宣教師との接点に注目することで戦国時代に生きた人々の心性に迫ろうとする画期的論考。【目次】まえがき――宣教師の注目した『太平記』/第一章 中世びとの『太平記』/第二章 『太平記』と日本人の心性/第三章 『太平記』と歴史/第四章 記憶の場「日本」/終章 国家と未来/あとがき/参考文献
目次
まえがき――宣教師の注目した『太平記』
第一章 中世びとの『太平記』
第二章 『太平記』と日本人の心性
第三章 『太平記』と歴史
第四章 記憶の場「日本」
終章 国家と未来
あとがき
参考文献
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
aloha0307
14
太平記と言えば、昭和の大河ドラマを思い出す。尊氏を演じた真田広之さん カッコよかったな(高師直:柄本明さんもすごかった)...いっときも定まらないケイオス&無常観 今でも大河のベスト1だと思っています。本書が論じるのは、宣教師と太平記の意外な関係だ。日本人キリシタンを養成するにあたり、イエズス会宣教師は太平記をその教科書としたのです。一寸先は闇、先の全くみえない現代とこの時代との符合にはっと気付き慄然としてしまいました。2017/05/14
浅香山三郎
12
『太平記』や『平家物語』の中世人にとつての受容の問題を取り上げる。宣教師たちの布教戦略の話から、中世人における『太平記』の規範意識などに話が展開する。「日本人」「日本国」意識の問題は、まう少し展開して欲しかつた。2018/03/21
ゆうきなかもと
10
太平記に関する本はめったにお目にかかれない。本屋で見つけてテンションマックス(^^) 太平記が、近世において平家物語と同じくらい、あるいはそれ以上に愛好されていたことを論証している。 平家物語に比べて、思想的に一貫性がないと言われている太平記だが、実はあるのではないかと言う指摘が参考になった。 太平記の解説書としてオススメだが、一般的には太平記はあまり読まれていないので残念に思う。 平家物語より面白いと思うんだけどなー(´・ω・`)2017/03/27
nagoyan
7
優。キリシタン版「太平記抜書」の存在から、日本語・日本文化を理解し、カトリック布教に役立てようとした宣教師・イエズス会の戦略を解き明かす。そして、そこから、太平記や平家物語といった軍記物語が当時の日本人の教養の源であり、日本人の精神文化を形作っていったことを導き出す。これはよくわかる気がする。江戸から明治大正にかけて、日本人の精神を作ったのは、歌舞伎であり、落語であり、講談であり、あるいは活動写真ではなかったか。歌舞伎、落語、講談そして活動写真を理解するためには、ある種の歴史知識が必要であったろう。2017/05/01
さとうしん
7
本書は実のところ『太平記』も宣教師の視点というのも取っ掛かりにすぎず(古典としては他に『平家物語』も取り上げられている)、戦国時代には共通の「歴史認識」と「日本人」としての国民意識が芽ばえつつあったのではないかというのが眼目となっている。戦国時代は乱世と言いつつも、南北朝時代などとは違って統一国家への展望や希望が見えていた時代なのかもしれないと思った。2017/03/21
-
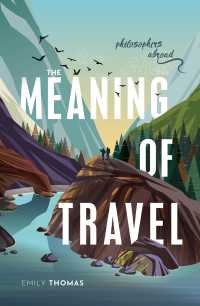
- 洋書電子書籍
-
旅の哲学
The Meaning…
-
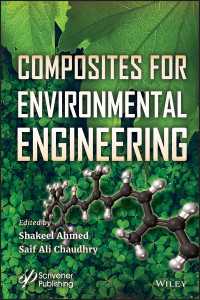
- 洋書電子書籍
-
環境工学のための複合材料
Com…