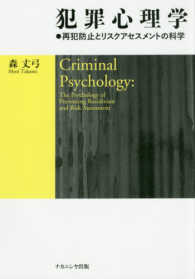内容説明
日本人は古来、石には神霊が籠ると信じてきた。庶民は自然石を拝み、石を積み、あるいは素朴に造型して、独自の多様な石造宗教文化を育んだ。仏教以前の祈りの時代から連綿と受け継がれてきた先祖たちの等身大の飾らない信心の遺産。路傍の石が体現する宗教感情と信仰を解き明かし、埋もれていた庶民信仰の深い歴史を掘り起こす。
目次
謎の石──序にかえて
第一章 石の崇拝
第二章 行道岩
第三章 積石信仰
第四章 列石信仰
第五章 道祖神信仰
第六章 庚申塔と青面金剛
第七章 馬頭観音石塔と庶民信仰
第八章 石造如意輪観音と女人講
第九章 地蔵石仏の諸信仰
第十章 磨崖仏と修験道
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
26
1988年初出。 石にも神霊(裏表紙)。 不思議なものへの畏敬。 上別府茂氏の解説によると、 日本仏教民俗学→宗教民俗学と称する(287頁)。 石が人間を見守っている。 そうした見守る存在の大きさは今の世でも必要なもの。 石には神仏や霊魂がこもるアニミズム(霊魂崇拝)が発達(20頁)。 日本人の目に見えない文化資本ともいえる。 現代は監視社会であるが、石も物言わぬ監視役といっては 語弊があろうか? カメラを設置するよりは犯罪抑止にならないか。 2014/03/29
テツ
24
超越者に祈りを捧げたいときに形がなければなかなか祈りに熱が入らない。姿のないものをそのまま信じることはなかなか難しい。だから人は古来から依り代として石を扱ってきた。石そのものには霊性はないかもしれないが、造り上げ磨き上げた石には力ある何者かが宿る。宿ってくれたと共同体のみんなで信じることができたのなら祈りは強くなる。信仰とはきちんとしたシステムなんだなと思う。現代人からは原始的に見えたとしても、そこには人の叡智と今ではこの世界から去ってしまった神様たちの姿がおぼろげに浮かび上がる。2019/11/14
らむだ
10
自然石崇拝や積石信仰、道祖神や庚申塔、馬頭観音や地蔵尊や磨崖仏など、主に日本国内でみられる“石”の宗教を概観。古代から連綿と続く信仰と感情を辿る一冊。2022/07/01
筑紫の國造
9
表紙からかなりのインパクト。文中でも解説されるが、これは「万治の石仏」というもの。本書では、我々が知っている仏教や神道以前の、素朴な庶民感情に基づく「民間信仰」について探求する。著者曰く、日本人の根底にある宗教感覚には「石」があった。「磐座」という言葉があるように、我々のご先祖様は「石」を聖なるものと考えた。こうした感情が、仏教以前というだけでなく、神道よりも前にあったという指摘は新鮮だった。無理やりインドや中国由来の仏教と結びつけて石の宗教を解説する愚もうなづくける。ただ、仏教用語にもっと解説がほしい。2019/06/11
はにゅ
9
賽の河原や洞窟に石を積んで供養とする信仰が多く紹介されています。また道祖神や庚申塔についても記述が多く、神道や仏教と原初信仰との関係が考察されてた。また、ストーンヘンジなど、世界の不思議な石との比較も多いので大満足な内容。歯に衣着せぬ書きっぷりは読んでて痛快。ただ、石積みによる願い石信仰の例が少なかったけど、他の資料をあたるか……2015/01/15
-
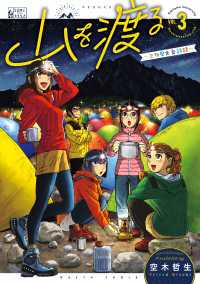
- 電子書籍
- 山を渡る -三多摩大岳部録- 3 HA…