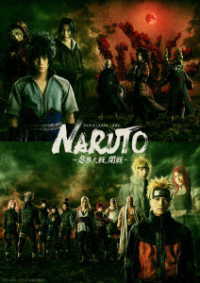- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
倭も百済、新羅、加耶などの朝鮮半島の国々の歴史も従来は、すでに国が存在することを前提として語られてきました。しかし近年の日韓両国の考古学の進展により、事実はそれよりも複雑だったことが明らかになってきました。交易の主役は「中央」ではなく様々な地方の勢力だったのです。倭一国だけを見ていては見えないことが、朝鮮半島という外部の目から見えてくる。歴史研究の醍醐味を味わうことのできる1冊です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
64
文献からではなく、考古学を通して歴史を再築する試み。弥生~6世紀まで、ほとんど文献の引用はなく、ひたすら発掘資料、発掘地の地理によって、朝鮮半島と日本列島の動きをとらえる。一貫して「国」ではなく「社会」と表記されていることが新鮮。古代国家として統一されているわけでもなく、そもそも国と言えるのかどうか(定義の問題でもある)を思えば、地域社会相互のつながりと考える方が理にかなっている。「任那支配」が現在の歴史学で否定されているのも当然だろう。2017/02/26
小鈴
33
興味深い内容なのに読むのにかなり手間取りました。その理由は明快で朝鮮半島の地理をわかっていないから。章ごとに韓国と日本の遺跡をすべて載せた地図が欲しい。自分が想像していたより古墳時代は半島との行き来があり、外交も大和王権が独占しているわけでなく北九州地域や吉備地域などとも。かならずしも百済というわけでもなく新羅とも。列島にも半島の古墳があったり。半島の統一の影響で列島の外交を大和王権が押さえていったり。半島からの介入があったり(新羅介入の磐井の乱。これにより北九州地域の外交が大和政権の手に落ちる)。2019/10/23
kk
28
いわゆる古墳時代の日朝関係について、半島の側から列島を眺める視点、中央政権だけでなく、半島・列島双方の地域社会が担った役割への視線、日朝間のやり取りを単なる外交としてだけでなく、より幅広い交流として見つめる視線。墓制だの葬礼だの副葬品の系統だの、本来的にめんどくさい事柄を扱っているものの、出来るだけ分かりやすく説こうという姿勢は特筆に値するんじゃないかな。日朝関係への思い入れと、古代史学者としての情熱を感じさせる。あとがきの記述が心地良かった。2019/07/06
活字の旅遊人
26
この先生の、素直な書きぶりに好感を持った。
浅香山三郎
21
任那といふやうな名前でかつて教科書に出てきた韓国南部の地域について、近年の日韓双方の考古学が明らかにしてきたことを丁寧に説く。地図があるとはいへ、この地域の土地勘がないとなかなかつらいところがあるが、百済・新羅・日本を繋ぎ、各々と墓制等に影響関係の見られる複雑な様相がわかる。2019/12/12
-

- 電子書籍
- ハイフロンティア【タテヨミ】第91話 …
-
![大学入試問題集 関正生の英語長文ポラリス[0 基礎レベル]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1400508.jpg)
- 電子書籍
- 大学入試問題集 関正生の英語長文ポラリ…
-

- 電子書籍
- 憂鬱なプリンセス〈華麗なる一族II〉【…
-
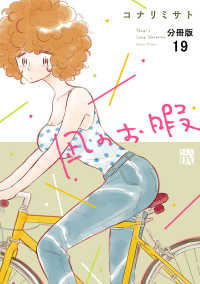
- 電子書籍
- 凪のお暇【分冊版】 19 A.L.C.…