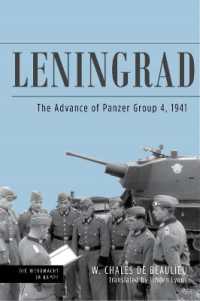内容説明
毛髪は人間の証、文化の象徴である。
人類が毛を失った理由、体毛の量と文明性、人毛売買の相場、最先端の毛根再生研究……
驚異の「啓毛」書!!!
人類はなぜ、ふさふさの体毛を失い、頭髪をはじめとする一部にだけ体毛を残したのか? 最新の研究では、高度に発達した人間の脳は、体温が41度を越えると「脳死」の危機に瀕するため、体温の急上昇を避けようとして体毛を退化させたという。つまり、体毛の退化は、脳を発達させ、文明を生み出していく前提条件であった。その意味では、人間が残した頭髪は人間の証であり、文化の象徴である。人間がハゲに悩んだり、髪型にこだわるのは、必然である。
本書は、毛の役割が人類に与えた影響を、生物学的、進化論的、文化的な角度から紐解いていく。また、頭髪にまつわる歴史上の人物の逸話から最先端のハゲ治療法までを網羅。
著者は学術的分野でも実際の現場でも最先端であり、日本の大手化粧品メーカーがIPS細胞を使った毛根再生医療の研究を行い、実用化に向けて準備を進めているなど最新のネタも盛り込まれている。育毛中心の実用書は多くあるが、一般向けに髪と人間の関わりを網羅した本は他に類を見ない。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
starbro
115
図書館の新刊コーナーで見つけて、興味をもって読みました。生物学的見地からの考察だけではなく、歴史的、文化社会学的等、様々な角度から「毛」を取り上げており、「毛」の奥深さを感じました。何千年前の人間も、現代の人間も未だに「毛」で悩んでいるなんて・・・「毛」が成長するメカニズムが完全に解明されるまでは、究極の毛生え薬は出来ないと思います(笑)私は当面必要ありませんが・・・2017/03/16
澤水月
27
犯罪・被差別者の髪を剃る、愛する故人の髪で芸術作品やジュエリー作る、米理容業と奴隷制などなど文化系からかつら製作の機微、毛がフェルト化する仕組みや犯罪での証拠価値、食品に入ってる人毛加工品!など最先端科学まで。キューティクルない毛を海苔がない巻き寿司に例えたり日本通だと思ったらアデランスで毛包再生の指揮をした経歴も。髪だけでなく羊毛やビーバー、ヤクの毛が人の歴史に深く関わったなども。入門、総合的とはいえ某「毛の鑑定が超絶びっくりオチになる密室殺人ミステリ」をあっさりネタバレしてるのに苦笑も2017/07/13
ユウユウ
25
今後、システインと食品添加物には注目してしまうかも。(アヒルの羽や人毛から作られるそうです。。。)単なる人類の体毛についてだけではなく、そもそも毛とはなにか、どのようにして生えるのか、毛が伝える意味はなにか、毛の性質とは、どのように利用されているのか等に加え、動物の毛や毛皮についての言及もある幅広い内容。知らなかったことも多く、面白かった。2020/07/25
zoe
20
HAIR-A Human History (2016). 毛幹について。表皮幹細胞と毛乳頭細胞が寄与。進化の過程で皮膚の表面が単層構造から多層になって生まれた。起源には3つの説があり、鱗、腺、感覚構造から生まれたと言われる。24種あるケラチンというタンパク質が糸状となったもの。根本の毛包は3層を成す。成長から脱毛までの周期を繰り返す。水に濡れると水素結合が切れ緩み、油を吸収する性質がある。また、作られた時の栄養状態などを反映する。キューティクルを利用し染めたりフェルトを作る。羊毛業界のために研究が進んだ。2020/05/30
奈良 楓
18
【とても良かった】読友さんの履歴で読みました。予想以上に面白い。 ● 著者はアデランスの米国研究所に携わったらしい。 ● 生物学的、歴史、経済と幅広い分野を抑え、なおかつ読みやすい。 ● 毛の生える仕組みがよく知らなかったことにこの本で気づきました。 ● ビーバーの毛皮ラッシュ。 ● 人毛の食品添加物への利用。 ● 個人的には、つむじが2つある知育発育不全と関係がある(かもしれない)に驚き。私そうじゃん、と思った。 ● かつらの技術の繊細さ。2022/04/22