- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「わかる」ことより、「わからない」ことを自覚していることの方が、はるかに重要である。何事にもスピードが要求されてきたこれまでの社会では、すぐに正解を求める。しかし世の中のことは、そう簡単に白黒つけられない。それを無理につけようとすると、どうしても、ありきたりの決まった答えに収まりがちになる。――<本書より>
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
♪みどりpiyopiyo♪
60
人間はいとも簡単に誘導されてしまう。メディアにおける議論の問題点を具体例で示し、「情報に騙されない」方法を平易に懇切に論じる書。 ■書棚整理に際して再読。巷で実しやかに語られるトピックを論理的に解きほぐし、矛盾や反証を示して丁寧に検証しているところが面白く、それらを受けての結論も納得感のあるものです。■一つの正解があると信じてそれらしきものに飛びつくのではなく 自分で考えて判断すること、常に情報を集めながら認識を更新し続けること。10年以上前の本だけと、いつの時代にも大事なことだよね。(2005年)(→続2018/05/30
tetuneco
14
「わかりやすさを求める傾向」の危険性を知る。なんでも早く早くと答えを求めてしまうことには、我ながら反省。2011/01/02
きむロワイヤル
7
少年非行の増加やゲーム脳の科学的根拠、ゆとり教育による学力低下の話などの常識と思われる話が実は根拠の薄い(あるいはまったく根拠のない)話であったというようなことがどうして起きるか、そのメカニズムを解説し、いわゆる自分で考えて判断することの大切さを教えてくれる。それにしても、あれだけ叩かれたゆとり教育は、次世代を見据えた教育の在り方の一つの解でそんなに間違った方向性を持ったものではなかったということは驚きだった。2015/11/17
スズツキ
7
面白い。少年犯罪増加、学力低下、ゲーム脳、携帯電話によるペースメーカーの影響など実しやかに語られている現象をデータの取り方などからその論拠の間違いを述べていく。巷での偏見の素になった『ゲーム脳の恐怖』が俎上にあげられているが、これへの反論の仕方は見事。2015/04/08
takyaC
7
第一章〜四章では統計、権威、時代、ムード、それぞれのウソが関係していた社会問題について触れ、同じような情報を見たときに何に気をつけるべきが書いてある。第五章は他の章とは少し印象が違った。その中でも、そもそも論理とは見方や立場によって正しいかそうでないかが変わる。不確定な論理を収束するためには自分の立場に自覚的になる必要がある、というメッセージが一番印象に残った。これから社会と関わろうとする学生さん達が読むといいかな。2015/02/05
-

- 電子書籍
- 異世界事故物件住みます、俺。【タテスク…
-
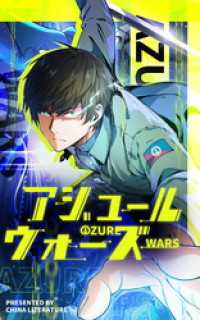
- 電子書籍
- アジュール・ウォーズ【タテヨミ】 10…
-
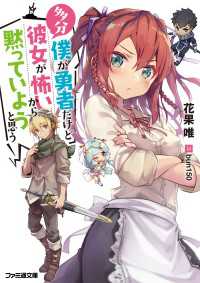
- 電子書籍
- 多分僕が勇者だけど彼女が怖いから黙って…
-
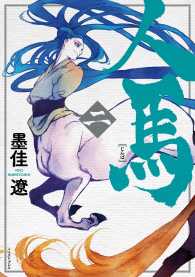
- 電子書籍
- 人馬 - (二)【電子限定特典付】
-

- 電子書籍
- ストライカーDX2016年11月号




