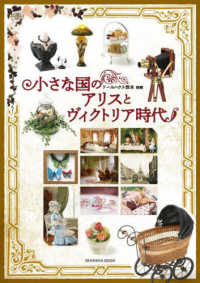- ホーム
- > 電子書籍
- > ビジネス・経営・経済
内容説明
経営学第一人者が書き下ろした
実践的な経済入門書
本書では、難しい数式は一切出てきません。
「経済を見る眼」を養うための入門書です。
人間の行動やその動機、また多くの人間の間の相互作用を考えることを重視し、人間臭い「経済を見る眼」を提示しています。
著者・伊丹敬之氏は「経済学とは人間の学問である」と述べています。
加えて、「経営の営みは一種の経済現象である」とも述べています。
「原油安でなぜ景気が悪くなるのか」「なぜ機関投機家が企業に過剰な影響力を持つのか」「生産性が低い『おもてなし』サービス産業は発展するのか」など、ビジネスの現場で遭遇する疑問に答えつつ、実践的な経済の考え方や見方を解説しています。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
5 よういち
107
経済現象を適切に理解し、考える上で必要な『経済を見る眼』◆平易な言葉で語られ、経済の入門書としてうってつけだと思う。ただ、決して低いレベルの話しではないので、何度か読みんでみないと理解できていない箇所が幾つもあった。◆この20年間で経済成長が見られない日本。マクロ経済の理論が通じない。『金利が下がれば、投資は増える』→家計も企業も投資は増えていない。政府だけが金を使い続ける。◆最大の原因は"日本人の心理的エネルギーの低下"。経済を見る眼を養うカギは、人間の行動やその動機について考えるクセをもつことにある。2020/08/09
koji
17
著者のこれから日本経済を担う若者への提言の書です。「経済とは人の営み」が著者の結論です。第5部に著者の想いが要約されています。私なりに参考になった点を列挙します。①ハーシュマンの「神の隠す手の原理」、②経済を難しくする3つの歴史的堆積(既得権益、資源の固定性、心理の粘着性)、③全体を眺めるクセをつける、④歴史は跳ばない(既知の論理で説明できない時背後のメカニズムは何かを考える)、⑤複数の論理経路を常に考える、⑥多様性は収斂する(多数意見に従う、資源の取り合いになる、ミクロの動機とマクロの振舞いを意識する)2017/11/29
owlsoul
9
経済統計は単なる無機物の測定値ではなく、人間の行動やその動機の表象である。一つ一つの現象は単純でも、それらは社会の中で複雑に絡み合い、互いに影響を与えながら予想もつかない結果を生み出していく。しかし、そんな複雑な世界も最終的にはどこかへ「収斂」されていく。市場で繰り返される取引と情報交換が雑多な意見をマジョリティ側に収斂することもあれば、利害の衝突から限られた資源を奪い合った結果、その分配が決まり争いが収束していく場合もある。つまり「経済を見る眼」とは、この複雑な経済社会が収斂する先を見通すスキルである。2024/09/23
まゆまゆ
8
人間を見つめることが、経済を見る眼を持つための原点である。彼らの行動を想像するために経済学の理論が役に立つ。カネ、情報、感情を等しく重要なものとして考えないといけない。日本経済をこの視点で解説していく内容で、読みやすい。供給側でいくら努力しても需要側が様々な要因で変動するので、好景気・不景気という波が生まれる、という説明が府に落ちたかな。2017/04/11
Kentaro
3
ダイジェスト版からの感想 日本の製造工程の技術の蓄積の成功は、人本主義企業システムは大きく貢献した。人本主義の日本企業が、現場を大切にし、人々の間の調整を大事にし、多くの人々の間の相互接触と相互刺激が大量に起き、日々の努力の積み重ねの中から小さな革新を積み上げていくことが出来た。現場の人々が現場での作業から学習するので能力が上がる。個々人や個々の職場が自分のセクショナリズムを主張することが少なく、みんなが周りの動きを見ながら自然に調整をとるので円滑に進み、情報が融合して、新しい情報へと変貌していけたのだ。2018/03/16