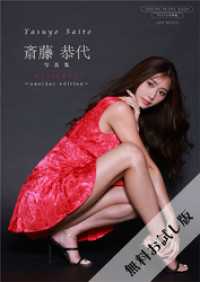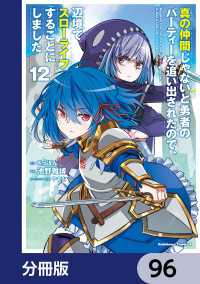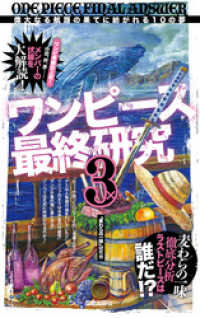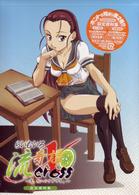内容説明
この本は歴史の教科書でもなく、京都の重要なことをまとめた集大成でもなく、ある特定の寺院についての解説書でもありません。観光ガイドや歴史書に出てくるような詳細な情報、たとえばお寺の開創年、アクセス情報、メインの見どころは述べていません。それより、私とキャシーが京都の表通りよりも裏路地を歩いて興味をもったものを追求して得た知識や情報を盛り込みました。(中略)この本で述べていることは、一般的に教わる日本と京都の歴史とは合致しないかもしれません。あくまで「口伝」であり、これまで誰も書き下ろしたことのないものです。(「はじめに」より一部抜粋)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
yyrn
28
表面だけ見てニッポンすごい!京都ステキ!というような外人の礼賛本とは一味も二味も違った本で、広く深くかつ長い時間をかけて蓄積されたであろう知識に裏付けされた京都の神社仏閣や建具に関する解釈や指摘は知らないことばかりで、京都再訪時には見逃さないよう精読してから出かけたい。▼能楽の「幽玄」、生け花の「天地人」、茶の湯の「和敬清寂」そして書から生まれた「真行草」は中国文化から脱して日本独自の美を確立させた証と教えられた。著者は「真行草」を楷書・行書・草書から転じたと説明しつつ「まじめ・ふつう・おかしい」と訳し⇒2022/01/30
なにょう
20
これは大した本だ。京都、日本文化の案内書。文字もぎっしり、ただ絵もしっかり挿入されてとてもわかり易い。★こんな本は日本人が書くべきだろう。日本人にとっては空気のようなものを(漢字、襖、屏風などなど)しっかり観察して価値を見出している。門から始まり、塀、襖、屏風なら何処を見るべきか。京都に行ったら、ただお寺に行くだけじゃなくて、襖とかの絵に注目するといいって。★そりゃ、京都に比べたら北京の方が宝物は多いかも。でも、紫禁城にしたって何処にしたって「遺物」p289キレッキレの比較文化論でもある。2017/03/19
trazom
16
この本は「門」「塀」「真行草」「床」「畳」「額」「襖」「屏風」「閻魔堂」の9章に分けて京都を分析。観光ガイドではなく、アレックス・カーさんらしい鋭い視点からの日本文化論である。日本の三門は扉もなければ両側もスカスカ(門じゃない)、屋根のついた塀への違和感、板と畳の使い分け、扁額の深い意味、襖から屏風への進化など、こうして外国人に指摘されてハッとしている自分が恥ずかしい。中には、真行草を欧米の「三」と同一視するなど賛成できない論考もあるが、まずは、背景が異なる者同士が指摘しあうことから、深い理解が始まる。2018/12/13
ムカルナス
8
門、塀、床、畳、襖、屏風etcに著者が見出した日本文化についての話。タイトルは京都であるが これらの日本文化が色濃く残っている京都の寺院を紹介しているのであって京都の話ではなく日本文化論。第三章の「真行草」が興味深い。中国から洗練された「真」の文化を受け入れてきた日本は本家にはかなわず、自らのアイデンティティーを「草」に見出し室町後期から簡素で素朴なものに美を追求、千利休にいたって遂に「草」=最高の美という逆転が起こる。世界中に真行草はあるが「草」を「真」にしたのは日本だけだと言う。2017/04/05
はなこ
8
門、塀、床、畳、襖など、私たちには当たり前すぎてあまり意識しないものに注目していて、こう見れば面白いんだとわかった。漫然と京都に行くのではなくテーマをもつということかな。2017/03/11