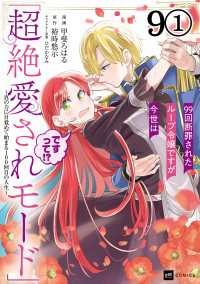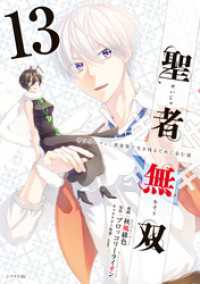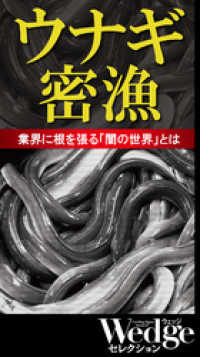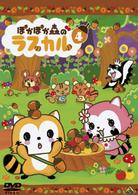内容説明
言語は、事実のコミュニケーションのための媒体であるばかりではない。言語自体がまた人間的事実であり、そこに集約されている著者の態度が精密に読み込まれてはじめて、読むことは十全な読書となる。論語・史記から契沖、宣長、徂徠にいたるまで、漢籍や和書を縦横にし、著者の内部に生起し蓄積する感情・思考・論理を通して内的事実に降り立つ実践を展開する。事実に触発される意識をたどり、読書論を超えて学問論にいたる。著者の悠然たる文学的逍遙につき随って、その思考の筋道をつぶさに経験する一巻。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
37
題名からすると、読書論のような感じを受けていたのですが、そうではなくご自分が読んだ中国の漢籍についての解説などをわかりやすく説いたものと考えます。月刊雑誌「ちくま」に5年にわたり連載されたものを1冊の本にしたようです。この本のようにじっくりと中国の古典について述べられるのを読むとやはり読みたくなる本がたくさんありますね。2014/12/30
1.3manen
20
底本1986年。支那文学がご専門の先生。てにをはは、弖爾袁波という漢字を書くようだ(053頁)。つゆ知らず。史学は人間の事実と事実の間の因果関係の究明、、それを方法とする学問(097頁)。本を読むには、著者を読もうということ(116頁)。著者の肉声をも想像しようか。ただし、言語は音楽ではないという(143頁)。過日は、数学は言語だという一節に触れたが、言語というものの考え方は一定していないということなのかもしれない。 2014/10/29
韓信
0
ハードカバーで読了。意識>言語>文章の順に不自由になることを前提に、文体・リズム・先達の註釈等を駆使した漢籍読解について綴る漢学エッセイ。論語の一節や史記に見える劉邦の顔立ちなどについて、日中の膨大な註釈・先行研究をもとに、迂遠なほど長々と編者の意図を読解していく吉川流訓詁学の書ともいえそうだが、読者にはハードルの高い内容だろう。劉邦を形容する「龍顔」だが、漢〜六朝では「顔」は額を意味したそうで、そうなると劉邦は竜のような額になり、どんな顔やねんと思うけど、これただの聖天子を象徴するレトリックだよね…。2024/02/24