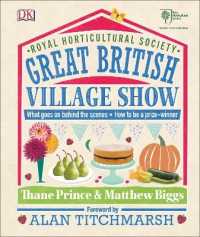内容説明
アメリカの作家エドガー・アラン・ポーの『モルグ街の殺人事件』(1841年)に始まる推理小説の歴史は、平成28(2016)年で175年を数えます。世界最古の小説といわれる紫式部の『源氏物語』が書かれたのが寛弘5(1008)年ですから、推理小説の175年という数字は、小説の歴史のうえでは決して長いとはいえないでしょう。けれど、名探偵シャーロック・ホームズを創始したイギリスのコナン・ドイルが登場してからというもの、推理小説はイギリスを中心に飛躍的な発展を遂げました。 日本における推理小説は、明治10年代に欧米からもたらされたところから歴史がスタート。明治26(1893)年頃に翻訳物、創作物合わせて一つの頂点に達したのち、停滞期を経て、大正10(1921)年に横溝正史が『恐るべき四月馬鹿』を、翌11年に江戸川乱歩が『二銭銅貨』と『一枚の切符』を発表すると、活況を取り戻しました。以来、推理小説は戦時中の10年ほどの空白を除いて発展の一途をたどり、その勢いは今日まで続きます。 一方、1830年、イギリスに誕生した鉄道は、明治5(1872)年にそのイギリスの指導を仰いで新橋~横浜間で開業して以来、大正時代には旅行の大衆化が一気に進みました。その後、第2次世界大戦で被害にあったものの復興し、昭和39(1964)年には東海道新幹線も開業。日本の経済を時に支え、時に牽引しながらその進展に貢献してきました。そして昭和50年代には国鉄が破綻、民営化されるという経過をたどりましたが、今は再び活気を取り戻しています。本書は、このような推理小説と鉄道双方の歴史と相関関係を踏まえて、鉄道を舞台にした作品、鉄道を主題にした作品などを総称して「鉄道ミステリー」と決め、これはと思われる作品を厳選したうえで時代を追って紹介します。推理小説と鉄道――この二つの相性が抜群によいこともあり、鉄道が重要な要素として、また格好の素材として推理小説に盛んに取り込まれるようになったことは、いわば必然の成り行きだったのでしょう。
■著者紹介
原口隆行(はらぐちたかゆき)
昭和13(1938)年東京生まれ。上智大学卒業後凸版印刷(株)に入社。
在職中より『鉄道ジャーナル』『旅と鉄道』などに寄稿をはじめ、昭和57(1982)年にフリーに。
著書に『時刻表でたどる鉄道史』『日本の路面電車I・II・III』『鉄道唱歌の旅 東海道線今昔』(以上JTB)、
『イギリス=鉄道旅物語』『イタリア=鉄道旅物語』(以上東京書籍・共著)、
『文学の中の駅』『鉄路の美学』『汽車ぽっぽ最後の時代』(以上国書刊行会)、
『最長片道切符11195.7キロ』(学習研究社)、『ドラマチック鉄道史』(交通新聞社)など。
目次
■本書の収録内容
第1部 探偵小説の萌芽と日本における発展
第1章 「探偵小説」の時代
第2章 探偵小説から推理小説へ
第2部 世相や社会を映す鉄道ミステリー
第1章 推理小説の中の鉄道ミステリー
第2章 草創期のイギリスの鉄道ミステリー
第3章 江戸川乱歩と同時代の作家たち
第4章 焦土の中で再び芽を出した鉄道ミステリー
第5章 鉄道黄金時代と符節を合わせて発展した鉄道ミステリー
第6章 日本の鉄道ミステリーを支える国鉄の定刻運転
第7章 終焉の時を迎えた国鉄と昭和天皇の崩御
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
ミヤト
いづむ
まさむね
エヌ氏の部屋でノックの音が・・・
-
![月刊少年マガジン 2017年11月号 [2017年10月6日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0474430.jpg)
- 電子書籍
- 月刊少年マガジン 2017年11月号 …
-

- 電子書籍
- 作りやすくて、おいしい家庭の味 やっぱ…