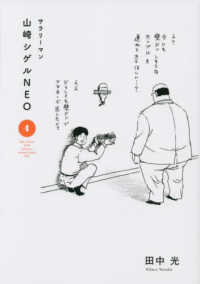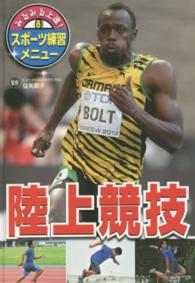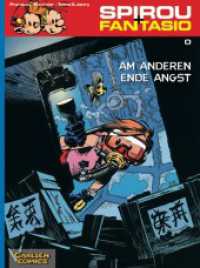内容説明
非線形科学──それは近代科学が久しく避け続けてきた「自然の生きた姿の記述」に挑む新しい科学だ。例えばホタルたちの明滅が揃う同期現象や、物質の濃淡が形作る自己組織化のしくみはこの科学によって解き明かされる。本書では、非線形科学を一つの切り口としつつ、この分野の第一人者がより豊かでみずみずしい科学の可能性を探る。そして、科学知をも超えた新しい時代の知のあり方にまで思考の翼を広げる。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
オザマチ
11
再読。昆虫や植物について考えると、未だに解明出来ていないことが多いことに驚く。本書のような問題意識が必要なのかもしれない。2024/07/17
Gokkey
9
現代科学の常套手段である全体を部分に分け、この部分の専門的理解に徹する。しかしこの部分を繋ぎ合わせても決して全体像は得られない。著者はこの問題に対して、切り分けた部分に与えられる主語とその時間的変化を記述する述語から構成される言語構造そのものから切り込む。このあたりのアプローチはハイデガーの影響を感じる。全体としての自然(ハイデガー的に書くならピュシス)を理解するにはどのような方法が可能なのか?その一つの答えとして例えば生命を非線形平衡系としてモデル化する試論が展開される。内容的にはストライクど真ん中。2023/11/17
オザマチ
9
数式がやたら難しいだけ、という印象だった非線形科学の見方が変わった。2023/11/07
愛楊
3
本書は、岩波講座「科学/技術と人間」の第四巻「科学/技術のニュー・フロンティア(1)」(一九九九年)に、「開放系の非線形現象」と題して筆者が寄稿した小論がもとになっている。現代物理学はまだラプラスの悪魔ではないということですね。最近の力学系の進展が気になった。2025/06/19
どさんこ
1
現在の科学に対するアンチテーゼを提案しているのだろうが、自分の理解が及ばない😮💨一方、この本の解説を書いている中村圭子の「生命誌」を以前買っていたが、この本も途中で投げ出したままだ😣じっくり再読しなければと思うのだが、果たして少しは理解できるのやら。2022/06/08
-
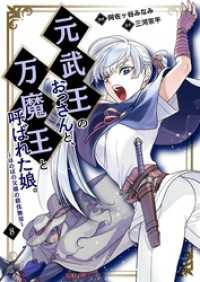
- 電子書籍
- 元武王のおっさんと、万魔王と呼ばれた娘…