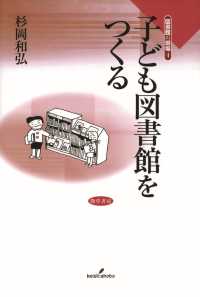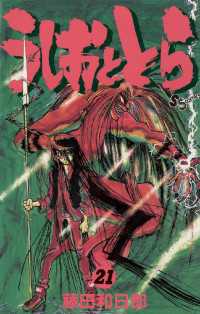内容説明
マーケティングの成功実例がここに! 若桜鉄道は、鳥取県東部の山里・若桜谷を走る第3セクターで、沿線に有名観光地はなく、過疎化、少子高齢化、そしてモータリゼーションの発達で経営は危機に瀕していた。そこに公募社長として東京から単身赴任で乗り込んだのが、著者・山田和昭氏である。外資系IT企業でのマーケティングやブランディング、地域鉄道会社の業務支援といった経験を生かし、全長19.2キロ、社員18人、保有車両4両という小さな鉄道会社の立て直しに挑み始める。2015年4月の「SLの走行社会実験」、2016年3月の中間駅名とスズキのバイク名にちなんだ「隼ラッピングカー」etc――地域と二人三脚のリアルな実践例は、鉄道ファンのみならず必読!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
18
巷にありがちな、単純な地域おこしとは、まったく似て非なる物語。立派なビジネス書でもある。現状、環境をきっちりと分析したうえで、地域住民の力や県・市・町、各種企業との連携など、ストーリーが描かれている。山田社長の前職での経験が活きているとはいえ、それだけではないものがある。それは、鉄道への思いと、永続することを念頭においていることかもしれない。それにしても、隼駅でのお祭りは、行ってみたいと思う。2017/10/01
さすらいのアリクイ
14
鳥取県内を走る鉄道、若桜(わかさ)鉄道の社長さんが社長になるまでの経歴、若桜鉄道の社長に就任後にチャレンジしたことなどが書かれた本。兵庫県内の町からSLを譲り受け、走れるかどうか検査し、社会実験としてSLを走らせたことが本の巻頭でのお話。そこからその実験の意味や狙いについてや、地方の小さな鉄道会社は情報発信や商品開発などであれこれの変わり種を仕込む必要があるというお話へ。アイデアの出し方、周囲の巻き込み方などを実際に行ったイベントを例に出しながら説明する部分もあり。マーケティングの本でもあるのかなと。2018/02/21
西澤 隆
5
田舎町に住む僕にとって「まちおこし」は身の回りで日々行われていること。でも一方で人は減り、熱気はどんどん薄まっていく。つまり「事例は山のようにあり、成功事例を見る事は少ない」話なのだ。山田さんにとってはこの本も若桜鉄道のブランディングなのだと思う。きっと大変なこともうまくいかないこともたくさんあるんだろうけれど、読んだ僕はしっかり胸が熱くなり、現地で乗ってみたくなり、そして自分も何かやりたくなる。マーケのプロが数字で田舎を騙すのではなく自分の技術を使って多くの人にさらに夢を見せる。こういう仕事、いいなあ。2016/09/29
Aby
4
交通は,住む人にとっては命綱である.中山間地域では,利用者が減って,その命綱がやせ細る.通勤・通学で利用できなくなると人が減る.悪循環.とはいえ,「でも自動車の方が便利だから」と言って使わないのも,そこの住民なんですよね.若桜鉄道は,地域の皆さんと一緒に生き延びて欲しいです.2016/11/01
ちゃいこ
4
苦境に立たされているローカル私鉄でも、様々な工夫でこんなにいろんなチャレンジができるとは。一度乗りに行ってみたい。2016/10/26