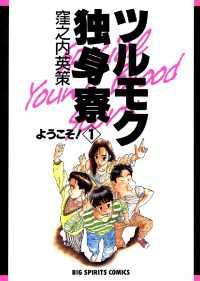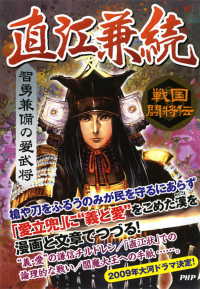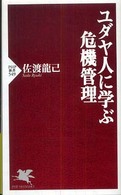内容説明
「改革開放」以降に海外に渡った「新華僑」によって形成されたチャイナタウンすなわち「新・中華街」が、世界中に増えている。アメリカ、カナダはもちろん、ロンドン、パリ、さらにイタリアや東欧でも、「食文化」を武器として現地社会に溶けこみ、強いコミュニティををつくりあげているさまを、異色の地理学者が現地レポート。さらに、新華僑を送り出している中国の町=僑郷も訪ね歩く。華人社会の海外での「「強さ」の秘密とは?
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まーくん
86
日本の中華街(横浜・神戸・長崎)は一応行ったことがあるが、新・中華街というのは知らなかった。池袋に有るらしい。世界のチャイナタウンは変貌しているという。改革開放後、新天地を求め国を出、新・中華街を作っている。それにしても何故、中華街は世界に拡がるのだろう?中国人の強い血縁・地縁の絆が理由であることは間違いない。著者は各地の中華街をフィールド調査と称して訪ね歩き、食べ歩く。彼ら華僑の故郷、福建省や広東省の「僑郷」も。学術的な論考というより完全にルポ。「楽しんで仕事をしている人は幸せだ!」と本人も言っている。2021/04/09
ようはん
21
思った以上に世界各地に中華街があり、パリやニューヨークの大都市だと複数作られる事も。華僑も世代交代があり特に改革解放後の若い世代は新華僑と呼ばれ、稼ぎにも精力的であるが故の問題も生じている。日本の三大中華街以外には池袋のチャイナタウンも知られているが、昨今の中国人の進出を思うと新たなる中華街が誕生するのだろうか。2025/08/02
ののまる
20
世界のチャイナタウンを見れば、その国の華人の状況がよくわかる。大阪では日本橋付近がチャイナタウン化しつつあるのだけど、あれはどちらかというと爆買いにくる中国人観光客向け店舗(なぜ日本に来て中国製の安い品を中国人店で買うのか??と聞けば使い捨て用らしい)で、それはチャイナタウンではなくてなんと呼べばよいのだろう。という具合に、カテゴリ化不能なほど、日々変容していく華人社会。訪日客がいなくなればさっさと閉店して他の稼げる国にいくであろう逞しさ。その変化にちゃんとついて行かないと完璧に置いてかれる日本経済。2016/10/20
さとうしん
10
横浜・神戸など旧来の中華街と池袋などの新中華街との比較、観光地としての整備によって中国人の街としての「リアル」を失ってしまった旧中華街、世界の新旧中華街、故郷に錦を飾る華僑のあり方、日本人に「魔改造」されるまでもなく、自分たちの力で現地化していく華人の食、「莫談国事」から転換しつつある華人の政治参加等々、華僑・華人をめぐる面白い地誌・民族誌に仕上がっている。2016/11/15
穀雨
6
地理学者の著者が、改革開放以降、世界各地に出現したチャイナタウンと、そこに暮らす人々を訪ねた、学術書というよりもルポのような本。中国人の地縁・血縁の強さと、中華料理の魅力がチャイナタウン発展の原動力となったことがよくわかる。あとがきで著者は、仕事を楽しみにできている私は幸せ者だと自ら述べているが、研究の一環と称してチャイナタウンの名物料理に舌鼓を打つ著者をみていると、確かにとてもうらやましく思えた。2020/04/21



![全国通訳案内士試験「英語1次[筆記]」合格!対策 (改訂版)](../images/goods/ar2/web/imgdata2/43840/438405095X.jpg)