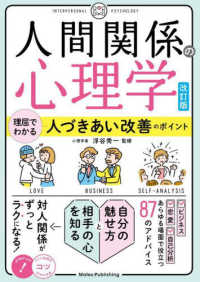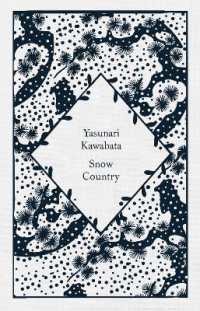- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「声」を複製し消費する社会の中で、音響メディアはいかに形づくられ、また同時に、人々の身体感覚はいかに変容していったのか――草創期のメディア状況を活写し、聴覚文化研究の端緒を開いた先駆的名著。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ハチアカデミー
11
ラジオは誕生当初、参加型メディアであった。多様な可能性を持った音響メディアが、国家主導のメディアへと変わる中で、一つの形へと落とし込まれていく。混沌としたメディアが資本主義化≒利用価値が高い方へ偏重することは、「文字」でも「映像」でも起こったことであるが、「声」に拘り、その統制が人間の感性や感覚に与えた影響を探る。「第七章 モダニズムと無線の声」では、アヴァンギャルドが音響メディアにどんな影響を受けたのかが論じられる。ブレヒトのサウンドコラージュとしてのラジオドラマという視点が面白い。文化史の名著である。2013/08/12
きつね
9
永井荷風の偏執狂的なまでのラジオ嫌いから説き起こされる聴覚メディア史。304「ゲッペルスのラジオ論が参照され…ナチのラジオ政策は、同時代の日本のラジオ観にも多くの影響を及ぼしていた。放送されるべき独裁者の声は空白のまま残されていたにもかかわらず、…戦時翼賛体制下の日本でも急速に広められていた」307「しかし…世界を断片化し、諸個人の内面とのつながりを失わせていったのは、かならずしもラジオという技術そのものではなかった…電子的な声の世界の成り立ち…電話は地域の日常的なコミュニケーションと絡まり合い、過去の諸2013/10/13
コウヘイ
2
電話やラジオといったメディアの誕生から社会のコミュニケーション技術として受容される様を描いたもの。論述の明快さはもちろん、1920年代〜1930年代当時の「声」をめぐる様々なトピックスも面白い。天皇の声がメディアに乗ることがタブー視されていた事実は、玉音放送の意味を考える上で大変興味深い。玉音放送の背景には、「ラジオ」というメディアがナショナルな情報流通システムとして確立されていた(そしてそのように国民が認識していた)ことが前提としてあったからこそ、当時の日本人にとって大きな意味を持ち得たように感じた。2023/07/14
dilettante_k
2
電話・ラジオ・蓄音機といった音声メディアの技術発展と社会的受容の歴史を辿る。音声メディアの歴史は、概ねアマチュアの試行錯誤にはじまり、市場性や求心力に注目した国家や産業に回収されるという過程を見せると言ってよい。このプロセスのうち、特にラジオ黎明期には、それが一方向性ではなく双方向性のコミュニケーション手段と捉えられていたことは注目すべきだろう。国家や産業が大衆化し、プロパガンダの具に貶めても、今度はアヴァンギャルドが境界を揺さぶり融解させる。今後のネット時代の「声」の行きし方を、過去から照射する良書。2013/09/16
k.m.joe
2
電話・ラジオ・蓄音機といった「声」のメディアの発達史。体制側より庶民の動きにスポットを当てている。それが逆に体制の醜さを浮かび上がらせる。残念なのは、私が元々理系に弱いせいか、あまり理解できなかった。著者のスタンスは分かるんだけどね。2013/03/17
-
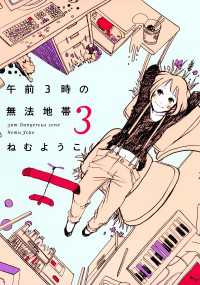
- 電子書籍
- 午前3時の無法地帯 (3) FEEL …
-

- 電子書籍
- 別冊Discover Japan - …