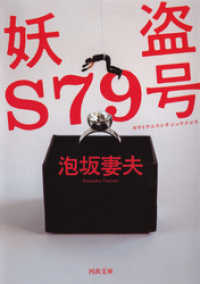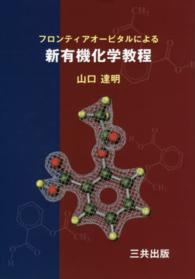内容説明
10万字以上の漢字のなかで、日本語の読み書きに使う目安となる常用漢字は2,136字。これに人名用漢字を加えた約3,000字で過不足はないのか。選択の基準はどこにあり、字体や音訓はどのように決められたのか。本当に常用されているのか。国家が漢字と音訓を制限することの功罪とは。本書は江戸時代の常用漢字を推測する実験から説き起こし、明治以降のさまざまな漢字表を紹介。常用漢字でたどる日本語の150年史。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Koning
32
気づいたらまた今野本だった(中公で売れてるからだしまくってる感じ?)帯の「常用漢字2136字+人名用漢字862字」ってのと「3000の漢字で日本語は書けるか?」というのは編集と営業的な何かで、明治期からの漢字使用制限に関しての歴史と今後の展望といった読み物。ローマ字表記は一見使われてないようでいて、ローマ字カナ変換を使っている人は実際には使ってるのと同じかも?とか言われてみりゃそうだ!な小ネタもありつつ、いかに文字数を制限してきたか「常用」されていた文字はどの程度だったのか?の時代による変遷も面白い。2015/11/24
さとうしん
10
文字通り明治以後の常用漢字表(的なもの)の歴史を追った本。字種の制限が、漢語表記や言い換えによる語彙の変化ももたらすこと、新たな基準によって字種を増やしても、変化する前の表記にはもう戻れないこと、漢字の制限は字体・字数だけでなく音訓にも及ぶことなど、盲点になりそうな問題について詳述している。2018/03/01
シンショ
5
正しい漢字とはなにか?と考えさせられる一冊だった。私も当たり前のようにPCや新聞等に掲載される活字が正しい漢字であると思い込んで過ごしてきたが、ある意味で人為的に正しい漢字とされたものを疑うことなく覚えてきたとも言える。もちろん誰もが画一的に漢字を覚えるために常用漢字は必要な措置ともいえるだろうが、知らぬ間にそれ以外の漢字は淘汰され多くの人が読めなくなり、逆に間違い漢字とされてしまう危惧もある。どの文章にどの漢字を使うも表現方法の一つであるから、簡単にテストの〇×で判断する怖さも感じた。2022/01/01
kawasaki
3
タイトルから想像する以上に広く、ことばと文字表記の関係や、ことばと文字の規範化の問題まで含む内容。無意識に使っているものを改めて意識化させられる。しばしば「伝統」に敵対する異様な説として切り捨てられるローマ化論や漢字廃止論も、日本語表記を模索する歴史的営みの中で据えられており興味深い。ちょうど外国人との日本語コミュニケーションを扱った荒川洋平『とりあえず日本語で』を読んだこともあり、誰もが使える(常用平易な)日本語表記と、古典にアクセスするための日本語表記の切り分けを考える。2016/01/23
asobi
3
高校時代に「肝心」を「肝腎」と書いてバッテン喰らったのを思い出す。納得いかなかった。当時は当用漢字で、漢字を制限するための制度だったから。この本を読むと今は肝腎と書けだと。明治の時代から漢字の制限の歴史が続いてきたことは勉強になったが、パソコンの時代こそ明治の文章がそのまま読めるような社会にしていかないと、文化的に衰退してしまうのではないだろうか。2015/11/25