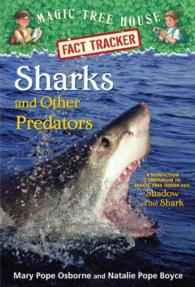- ホーム
- > 電子書籍
- > 趣味・生活(スポーツ/アウトドア)
内容説明
次の100年に向けて歩みを始めた高校野球。
勝利と教育のどちらも追い求める指導者13名の
「いまどき世代への指導法」とは―。
2015年に100周年を迎えた夏の甲子園。
時代背景とともに指導方法も移り変わり、
「根性」「理不尽」「忍耐」「スパルタ」といった言葉よりも
「自主性」「主体性」「自立」などの言葉がよく聞かれるようになった。
ただ、一方で「厳しい指導ができなくなった」
「最近の子は我慢強さがない」「打たれ弱い」という
悩みを抱えている指導者も多くいると聞く。
「ゆとり世代」「スマホ世代」「さとり世代」など
さまざまな呼び方をされる、いまどきの高校生。
果たして、彼らの力を引き出すにはどんな指導が必要になるのだろうか―。
-目次-
■大渕隆×本村幸雄(北海道日本ハムファイターズ)
■馬淵史郎(明徳義塾)
■森士(浦和学院)
■長尾健司(高松商)
■佐々木順一朗(仙台育英)×須江航(仙台育英秀光中)
■狭間善徳(明石商)
■中山顕(日立一)
■平田隆康(向上)
■齊藤博久(桐蔭横浜大)
■渡辺元智(横浜)×上田誠(慶應義塾)
目次
表紙
はじめに
目次
大渕隆×本村幸雄(北海道日本ハムファイターズ)
馬淵史郎(明徳義塾)
森士(浦和学院)
長尾健司(高松商)
佐々木順一朗(仙台育英)×須江航(仙台育英秀光中)
狭間善徳(明石商)
中山顕(日立一)
平田隆康(向上)
齊藤博久(桐蔭横浜大)
渡辺元智(横浜)×上田誠(慶應義塾)
おわりに
奥付
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Kentaro
38
横浜の渡辺元監督は言う。「高校野球はなぜ坊主なのか?」と聞かれることがあるが、そのひとつには「我慢を覚える」という理由がある。何でも、自分がやりたいようにはできない。我慢強さと関係するが、最近の高校野球はいいときはいいけれど、少しでも崩れると踏ん張れないチームが多い。 「使わない筋肉は滅びていく」という言葉のとおり、精神的な面も使わなければ退化していく。つまりは、我慢しようとする機会がなければ我慢する力は弱くなっていく。時代とともに手法を変えるのは当然だが、昔から引き継がれてきた精神面は大事にしてほしい。2020/06/10
ヤエガシ
6
非常に面白い本でした。高校野球を中心に、学生野球の強豪チームの監督に、選手への指導について話を聞いているのですが、人によって考え方がけっこう違っていて、ある監督が肯定していることを、ある監督は否定していたりして、「そうだよなぁ~、山に登る道は1つとは限らないよな」等、色々と考えさせられました。特に、高松商の長尾健司監督の章から、学ぶことが多々ありました。高校野球とタイトルに入っているので、野球本的な雰囲気が漂っていますが、中身は普通の会社員が読んでも勉強になることばかりだと思います。2017/02/15
gotomegu
5
高校野球の監督ですごいひとがいるって話題に登ったのがきっかけで読んだ。けっきょく、この本の中にはそのすごい三重県の監督は登場していなかった。高校野球って人気が落ちつつあるけど注目度は高い。高校生たちをどうやって馴らしているのかを語った本。根性とガマンが大事と言ってる監督が多数。そういう風潮が自殺者の多い社会を作ってる気がするんだよね。社会に出れば不条理はいっぱいあるのだから、不条理なこともよしとする監督がいる反面、ドラッガーのマネジメント小説さながらに組織全体で高校野球を戦う神奈川向上高校は印象的だった。2017/08/17
とこ
3
世代が変わっても伝えるべきことは変わらない。心の教養、勝負へのこだわり。今の学生は、先生以上の知識に囲まれている。自ら学ぶ力を育て、伝えて動かせる。年長者の人生に基づいた言葉は、私たちが知るべき本当の言葉だと感じます。2018/07/22
koya
2
どの監督も言っていること「競技だけできればいいということは絶対にない」ということ。将来社会に出てからも力となる人間力が必要だと言う。野球を通して、挨拶や整理整頓など当たり前を身につけることが競技の成果にもつながる。勝利の喜びを味わうだけで終わらず、これからの人生の力をつける指導が大切。2020/05/16
-
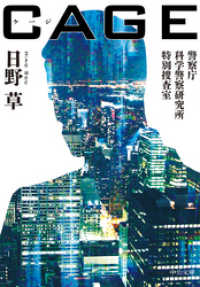
- 電子書籍
- CAGE 警察庁科学警察研究所特別捜査…
-

- 電子書籍
- 死神見習!オツカレちゃん ストーリアダ…