内容説明
福島原発事故を引き起こし、莫大な損害補償を負い、実質「国有化」された東京電力。戦後60年間、9つの巨大電力会社は地域の経済団体の会長を務めるなど社会的、産業的に日本の支配者といえる存在だった。1990年代と2000年代にわたり、国は「電力の自由化」と「核燃料サイクルの見直し」を電力業界に求めてきたものの、2度とも失敗に終わった。しかし今回の原発事故を契機に、60年間封印されてきた日本の電力制度が変わろうとしている。本書は、70年代オイルショック後の電力業界と政治家・官僚・メディアの闘いを電力制度や原子力制度の変遷とともに描く。日本独特のエネルギー政策のあり方と今後の課題を、欧米の電力業界――自由化された制度、脱原発、自然エネルギー――との比較を交えて分析する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
coolflat
4
前半の部分は電力の社会史というより、原子力の社会史という面が大きいように感じた。この本の一番のポイントで、個人的に最も参考になったのは、海外の電力自由化、特に発送電分離についてだ。海外と日本国内を比較してなぜ日本の電力自由化ができないかが分かる。他の本ではドイツの電力事情を取り上げているが、本書は普段お目にかかれない英国を取り上げている点でもポイントだ。脱原発への鍵は電力自由化だ。とにかく原発と自由化は相性が悪い。相性の悪さは2つある。コストと、1日中発電し続ける原発は自由市場に向かないということである。2013/10/06
かつばやし
3
9電力体制確立の歴史、日本の原子力事業の変遷、海外の電力自由化の事例、自然エネルギーの可能性など、戦後の電力に関わる事例を包括的に取り上げている。膨大なデータを整理し、明快な主張を盛り込んでいる良書だ。特に英国での電力自由化の例などを知ると、日本の電力自由化がいかに生ぬるくまともな議論がなされていないかがよくわかる。日本社会の変化の原因は「外圧(開国と明治維新、敗戦)」と「人柱(戦争や公害)」の二つであるとの記述が印象に残った。自分たちの議論によって社会を変えていくことが今の日本には求められているようだ。2013/05/09
じゅんぺい
2
この新聞社らしい原発への論調であったが、電力を取り巻く歴史がよくわかる本であった。発送電分離までの電力システム改革の経緯をよく取材されていてリアルだった。再エネに関しては、風力発電大量導入、接続可能容量の明瞭化という視点であった。風力が太陽光よりも世界的に多いことはあまり知らなかった。2020/07/10
かつばやし
1
7年ぶりの再読。改めて読んでみても、古さを感じさせない良書。この7年で、電力業界を取り巻く状況は確実に変化してきている。他国とはまた違った道を進む日本型の電力システム改革は今後どういった道筋を描くのだろうか。2020/03/07
すのす
1
電力会社だけでなく、政策サイドや、チェルノブイリのその後に触れていて、守備範囲が広く、豊富な記載。2017/09/30
-
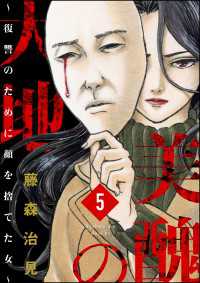
- 電子書籍
- 美醜の大地~復讐のために顔を捨てた女~…
-
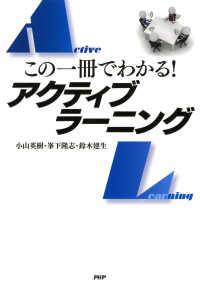
- 電子書籍
- この一冊でわかる! アクティブラーニング







