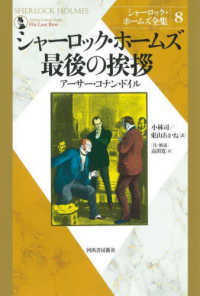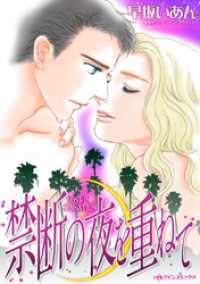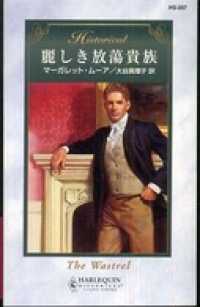内容説明
『正法眼蔵』で知られる、日本を代表する禅宗の泰斗道元。その実践と思想の意味を、西洋哲学と日本固有の倫理・思想を統合した和辻が正面から解きほぐす。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
jjm
11
NHK深夜ドラマ「ここは今から倫理です。」を見ていたら、道元の身心一如が出てきたことと、タイムリーに和辻哲郎の道元をお読みになっていた読友さんがいてピンときて手に取る。道元については元々ほとんど何も知らなかったが、考え方ががらりと変わった。彼は「何になる」を繰り返し問い、専心打坐に至った。それが仏祖自身の修行法であり、その直伝の道であるから。仏陀の正伝(を自負)なので、宗派を名乗らかったと言うし、仏教芸術を否定していることからも、宗教家というよりは釈迦哲学実践者というのが近いのかもしれない。2021/03/06
うえ
11
「もとより道徳への関心は、絶対者との合一を目ざす宗教にとって、第一義のものではない」「道元の道徳の言説には、もう一つ著しい特徴が認められる。内面的意義の強調がそれである」「道元の考え方はやがて仏教の芸術的労作を否認することになる。聖徳太子と法隆寺とによって推測せられる推古時代の仏教…降っては貴族の美的生活に調和した藤原時代の仏教、これらを通じて著しいのは、彼らの法悦がいかに強く芸術的恍惚に彩られているかの一点である」「道元は「日本国にひとつのわらひごとあり」として、女人禁制の道場のあることをあげている」2016/01/12
nomak
10
信仰から独立した、学問としての仏教哲学史が存在しないとを痛感した和辻哲郎。仏教ワクチンを少量ずつ接種してきたので、いまなら読めるとチャレンジしてみたが、まだまだ勉強不足で、なかなか付箋を貼れなかった。数少ない収穫は「ことごとく有るということは、有無の上である」衆生の中に仏性があるのではない、仏性の中に衆生がいるのだから、観ずることなどできないという解説に、梵我一如に対する道元の手がかりがある。「明日死ぬかも知れないのに、生命にしか価値がないのなら、価値なきに等しい。」無に対してまだまだ勉強不足だ。2021/02/22
たびねこ
10
視点が定まらず、最後まで難解。道元を哲学者として捉えようと試みたようだが、「道元の叙述を企てつつ途中で挫折」と本書内で正直に述懐している。2019/03/22
shimashimaon
7
親鸞の他力本願と比較する作品が複数あることを知って、読んでみようと思いました。和辻哲郎博士の著作なので心して懸りましたが、前半は比較的読みやすいと思いました。後半の道元哲学の解析からは難解になります。面白いと思ったのは、仏教の「法」(真理)は探究すれば到達できるものではなく、それそのものは不可知だが人格がその器になることはできるので、そういう人を見つけ出して師とすることが正しい修業(自力)の道であると説いた点です。仏教僧(救いの追求者)というよりも、哲学者(論理の探究者)であったということがわかりました。2022/08/20