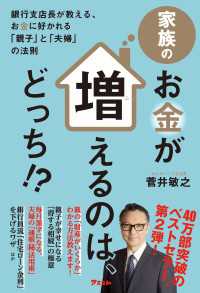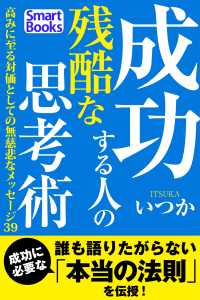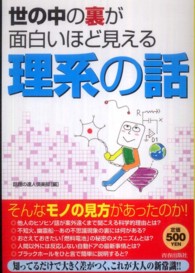内容説明
『不思議の国のアリス』と『鏡の国のアリス』――ふたつの作品には論理学者だった作者ルイス・キャロルがちりばめた知的お遊びがいっぱい。子ども向けのおとぎ話をよそおいながら、立派な教訓などは出てこない。論理といっても屁理屈といってもいいけれど、作者がしかけた知的遊戯を、さらに徹底的に論理的に考えてみると……。アリスと分析哲学と、一冊で二度おいしい哲学書。もしかして作者は映画や絵本よりこっち寄りだった!?
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
またの名
13
意味のないナンセンスな言葉遊びの児童文学を些末で煩雑な言葉の議論に延々と従事する分析哲学で解説するのは、ありそうでなかった良い組み合わせ。自分が二人いるふりをするアリスの論理は可能なのか確かめるだけのことに、別々の人物x≠yが成立する条件はp1≠p2となる場所p1にxの、p2にyのすべてが存在するというのでは足りないから別の条件を更に思考し、等と続ける空論もキャロル相手なら許される。突飛な世界を分析していった先に常識へ戻る分析哲学の弱みはナンセンスを存在論まで高めたドゥルーズにはかなわないけど、面白い本。2017/06/06
evifrei
10
不思議の国・鏡の国のアリスのシナリオを題材に、分析哲学的考察を行う。14章の『無と空』が特に面白い。八木沢先生の哲学書はユーモアに富んだ快活な筆捌きで書かれているが、本書も八木沢節がきいていて非常に楽しめる。内容は概念を分析するという分析哲学的の性質上ある程度難しさは伴うが、論理的な議論のもとにパズルを解いていく様な面白さはあるので、抽象論に留まらない哲学や明るい哲学が好きなタイプの方には是非おすすめ。強迫観念的な要素がなく、仲間や信頼できる教師と共に議論をしているかのような読書時間を過ごせるだろう。2020/02/27
アリス
8
卒論の文献に使用。2023/12/13
ひつじのよう
3
よ、読み終わった。後半の章になるにつれ難しいと感じるようになり読み進めるのが大変だった。しかし大好きな不思議の国のアリスでここまで議論を発展させることが出来る分析哲学という学問、非常に面白いと思った。考えたこともないような、または当たり前だと思うことがどのようにしてその結論に至るのか、その過程が大事で面白い。2019/05/06
take
2
青山拓央『分析哲学講義』に挫折したので本書を読んだ。『分析哲学講義』よりは分かり易いが、提示された話題に「自分の興味」がどうしてもついていききれない。永井均『私・今・そして神』や野矢茂樹『哲学航海日誌』を読んだ時も同じような感想を持ったので、この分野(?)が向いていないのかもしれない(でも、大森荘蔵の著作は面白かった)。もう少し粘りたいので、次は『功利主義と分析哲学』を読む。2018/01/30