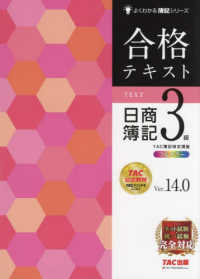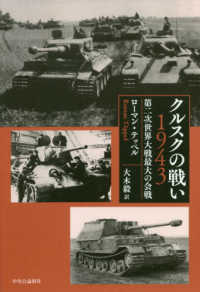- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
挫折しないことの不安におびえつつ、国家と共に至福の青春を生きてしまった森鴎外が、一切の社会的令名を拒否して死に至る凄絶な生涯。外的な役割も帰属の場所も信じられず、さりとて「子」の立場の甘えにも安んじることのなかった彼が、自己の内面の空虚に耐えた秘密は何だったか――。作家の生活と作品の間を照射することで、近代知識人論に画期的な視座を提起する、記念碑的評論。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜間飛行
210
長男として家人に期待され、明治天皇の激励を受けてドイツに発った鷗外。早期の留学生だった彼は国家との一体感を体験しつつ、反面、西洋近代への不信や国家との乖離も感じていた。後年、漱石が嚢の中に籠もるようにして留学を終え、また荷風が何一つ為すべき事のない己を発見して帰国したのに対して、鷗外は《自我の陰画》を実感する端緒がなく、彼ら二人のように居直る事もできず、〝闘う家長〟として生きるしかなかった。彼は日本文化や西洋文化を信条にしたり啓蒙したりする観念的態度を廃し、現実の中で自我の空白を凝視する険しい道を選んだ。2022/08/11
k5
50
山崎正和さんの文章が好きで読んでみました。冒頭の鷗外、漱石、荷風の明治における自分の役割捉え方、というか青春の生き方の部分はぐっと惹きこまれたのですが、ちょっと個人のエピソードが多すぎて後半疲れてしまったかも。でも、この知性のあり方はもうちょっと掘ってみたいと思います。あと、ほぼ読んだことない鷗外読もう。2025/12/20
ころこ
39
著者は鴎外を評価し、漱石を評価しない。生育期に読んだどちらかが実存的な悩みに応える様にしてその後の読書歴を形作り、作家や批評家になっている。漱石が個人の問題に拘れたのも、国家が自明でなかった鴎外の時代を経て、国家と個人が対立することに疑問の余地が無くなっていたからだ。鴎外の家長としての闘いの方が漱石の苦悩よりも差し迫った問題に直面している。エリートの慰みとして文学に全身全霊を傾けない鴎外の姿はポーズではない、と普通はみえる。ところが鴎外は「公」と「私」に、「政治」と「文化」分裂した前者を代表するといわれる2022/11/16
スナフキン
8
若い頃から憧れて止まない山崎正和先生による森鷗外論。本文も、引用される鷗外の文章も難しいが、それでも読んでいると、現実を忘れて、癒されるのを感じた。社会的な成功を収めた鷗外の、全く他人に理解されない孤独や絶望にくらべれば、私の孤独や絶望など高が知れている。そう思うと、気が楽になった。私も鷗外や山崎正和先生のような大人になりたいと思った。2022/05/09
Kiichiro YASUHARA
3
森鷗外は私のような教養のない人間にとって馴染みがないのだが、本書を読んで血肉ある人としてようやく感じられるようになった。近現代日本で改めて西洋と出会い漱石はどう、荷風はどう、鴎外はどうというと、鴎外は自ら親和的なこれまでの没個人の日本を捨てずに発見したのだった。現代の我々は孤独な個人主義にいるのだが、鴎外の知る日本というのはそういうものではなかった。そういう視点は現代に生きる人に改めて提示されるべきものだろう。森鷗外は素晴らしい人だったと本書を読んでようやく理解する。2023/03/15
-

- 電子書籍
- RM MODELS 296号