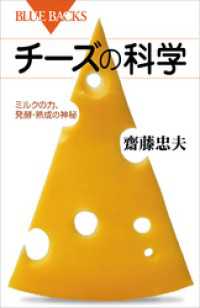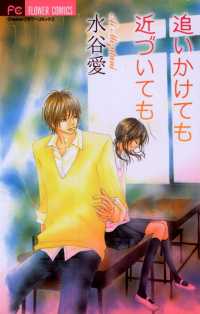内容説明
だれもが「かし」と呼ぶ隅田河口のまちに、ひとつの秘密を抱いた青年が住みついた。そこに住む人にとって、「どこの誰か」よりも「どんな誰か」が大切なまち。そんなまちの心優しい人々とともに彼は暮らし、〈秘密〉から解放される日の来るのを待っていた。心ならずも魚河岸の町に身をひそめた青年と、まちの人々との人間模様を情感こまやかに描き出した長編小説。直木賞受賞作。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
遥かなる想い
171
第94回(昭和60年度下半期) 直木賞受賞。 河岸通りに住む 人々の心の交流を描いた短編集。 現代には見られない商店街の 人々の掛け合いがむしろ 新鮮である。確かにそんな 時代があり、でも遠くなって しまった…近所の人々が 抱える悩みと哀しみ、そして 支えあう心…江戸の雰囲気が、 古き良き時代の風情が そこかしこにある…そして、 吾妻健作をめぐる秘密と 人生、学生運動盛んな時代を 彷彿させてくれる、味わい深い 本だった。2014/07/20
浅葱@
56
「このまちでは、どこの誰かよりも、どんな誰か、を大切にしている」ちょっと控えめな人たちの経緯(いきさつ)。「かしのまち」の人情。生きてきた確かさ。出来事からの出発。鰹節問屋の息子、吾妻健作の謎。今回も読み終えて清々しい気持ちになっています。→2014/02/28
BlueBerry
55
ちょっと有り得なさそうな設定なんだけれど違和感なく楽しめました。町の人達との交流とか限定されている分だけ逆に濃密で上手に描かれていたと思います。ラーメン屋台のおじさんとの交流が特に好きだったかな。これは割とお勧め。序盤○中盤◎ラスト○総合◎2015/01/04
天の川
25
1970年代から80年代の魚河岸に生きる人々を描くこの本は、地味ながら非常に上質でした。各章で主人公となる人々が抱える後悔や諦念、希望や秘密…他の章で脇役として登場する時、その抱えるものを考えます。現代の名言に選ばれていた伊集院静さんの「人はそれぞれ事情を抱え、平然と生きている。」という言葉を思い出しました。闖入者ともいえる吾妻健作の正体が次第にわかっていく構成も面白く、その事情が時代の空気を裏打ちしていました。最後の手紙が朝もやの中の旅立ちを感じさせてくれ、読後感も良かったです。→2014/04/09
あきあかね
22
魚河岸、という懐かしい響き。築地から豊洲へと場所は変わっても、本書のような人情味は昔と変わらずにあってほしい。 築地の市場に暮らす様々な人びとの群像劇。それぞれの話に、秘密を抱いた青年がいつも関わってくる。他のまちから追われるようにやって来た青年を優しくまちは受け入れ、学習塾の先生となった青年の知見や言葉は、まちの人たちの抱える問題に解決の糸口と、一歩を踏み出す勇気を与える。 「わきからでなく、真っ正面から人間に取組んだ連中、たとえば合戦で、生きるか死ぬかの最中に居る武者なんかですとね⇒2021/07/04