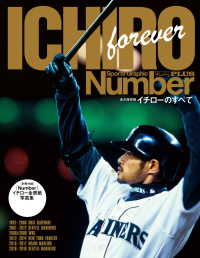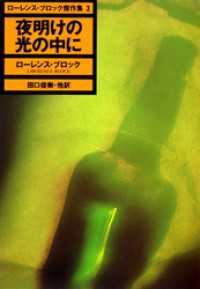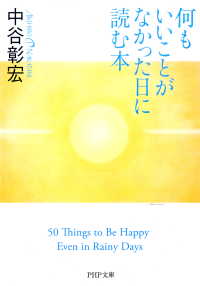- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
私大の両雄躍進の秘密とその課題を徹底解剖。階層固定化社会の象徴としての慶應。拡大化を図る早稲田。戦前、帝大の後塵を拝していた両校がなぜ成功を収めたのか。格差社会論の権威が解く、名門私大の経済学。(講談社現代新書)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mitei
256
日本を代表する2つの私大について書かれた一冊。歴史的背景から中々面白い。しかし今後はどの大学も大変だろうなと思えた。2018/08/16
佐島楓
50
カラーがまったく異なりながらも、私大のトップエリートとされてきた両校。創立の歴史や付属校からの内部進学者の動向を分析している。やはりOBとOGが多数実業界に存在する強みはあるのだなと改めて思う。2015/12/10
Nさん
4
2008年刊行。格差研究を専門とする経済学者が、早慶をフックに今後の大学に求められるものを考える一冊。創設者としての福沢と大隈の建学精神が後々の歴史・校風に大きな影響を与える。財界の慶応と政治マスコミの早稲田といったイメージ。なぜこの二校なのか?①共通一次試験の導入(国立大の5教科7科目)に対する私立大入試の負担感の少なさ ②国公立大との学費の差の縮小(かつては4〜5倍も現在は2倍)③東京集中化 などが私立大の人気上昇に寄与し、その中でも歴史(伝統)ある二校+他のブランド化を強化した。(→続く)2025/01/16
うえ
4
「安倍(磯雄)にとって同志社在学中に新島譲に感化されて、キリスト教信者になったことは画期的なことであった…卒業後、同志社の教員になったり、キリスト教の布教活動を行ったりしていたがアメリカの…神学校やベルリン大学に留学したことで転機が訪れる。帰国後…東京専門学校(早稲田)に移り、長い間教授を務めた……安倍は社会民主党を明治34年に結成する。安倍の『社会主義者となるまで』によると、世のなかに貧乏人が多くいることを知ったことと、同志社大学在学中に受けたキリスト教的博愛主義の影響が大きい、と述べている」2017/05/25
くりのすけ
4
両校の特徴がうまく整理されて書かれている。早稲田、慶応ともに実力ある学生が多いのがよくわかった。早慶が大きく躍進した背景には、共通一次試験の廃止や私学助成金の充実があったこともよくわかった。創設から現在に至るまでの両校の伝統が垣間見えた一冊だ。2015/06/27