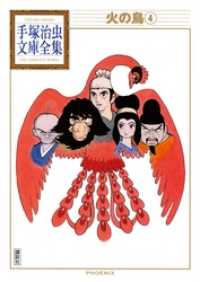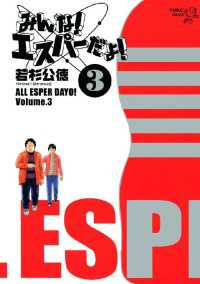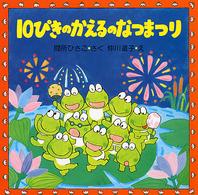内容説明
鎌倉中期、執権・北条時頼が権力を振るう頃。仲間たちと唄や踊りの芸を売って自由に生きる傀儡女・叉香は、復讐のために鎌倉を目指す武士や、武士に家族を殺された瀕死の女、信仰の本質を追い求める西域から来た僧らと出会う。全く異なる境遇で生きる四人の男女の運命が、鎌倉で交錯する。仏教と武士道が権力と結びつき、大きな流れを形成していった歴史の分岐点を舞台に描かれる渾身の歴史長篇。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
エドワード
24
もののけ姫の解説を書かれた網野善彦先生の「無縁・公界・楽」を読んだのは三十年以上前。大学のゼミだった。この作品は先生の斬新な中世史観を取り入れている。歴史は権力者と農民だけが生きたのではない。非人と呼ばれる、商人、山賊、修行者、遊女、清目、病人、芸能の民などの大勢の漂泊の民衆も必死で生きた。タクラマカン砂漠から来たサイラムが魅力的だ。彼を通じて<色即是空><躍念仏><悪人正機>を理解することが出来る。題名の傀儡はダブルミーニング。旅の芸能民と、日本史を貫く闇の権力。終幕に最も有名な今様が現れる所が上手い。2015/02/03
tama
11
図書館閉架本 面白かったがなかなかに混み入った作りとなってて、友人のいうように「あっという間に読み終わり」はしなかった。五代目執権北条時頼の頃の鎌倉。親鸞は出るわ日蓮は出るわ。念仏宗がいて中央アジアの坊さんが、念仏踊り始めたり(一遍じゃないのか!?)、南無阿弥陀仏は方便であると言ってみたり、物凄い。なかなか死なない女は何度も刺されたり切られたりしながらも生命力も体力も抜群。書いた方も読む方も相当エネルギーが必要。でも面白かったから読み通せた。著者もっと生きて欲しかった。2022/12/29
あいちょ。
8
かなりほったらかしてました。 改めて、坂東サンは凄いなと。 惜しいですね。2014/04/17
yonemy
5
禅宗についての理解が深まった気がする。「人は常に失うことを恐れている」は真なり。「死を潔しとする武士にはぴったりな教え」に頷く。仇討ちを狙う2組の執念がすごい。宗教でも仇討ちでも、なにかに取りつかれたように生きる人々と、傀儡者の軽やかさとの対比が鮮明だった。途中気付いて数年前の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』を思い返しながら読んだので、記憶に残りやすかった。2025/07/08
kuppy
4
実際の権力者が天皇でなく上皇、将軍ではなく執権という構図は日本特有なものなのか?黒子(フィクサー)と傀儡が重なり合って恨みの連鎖という人間の業が展開していく。網野さんの中世史観に大きな影響を受けたようで、鎌倉の源氏から北条摂関家へと変わるうねりの中で生きる底辺の人々(傀儡師、非人、遊女、戦乱に放浪される農民など)が丁寧に描かれています。もう一つの大きな流れが仏教で、公家、武士層中心の禅宗、広く平民に広がった浄土宗や日蓮宗、踊り念仏というのも宗教の高揚感を感じる。2021/03/01