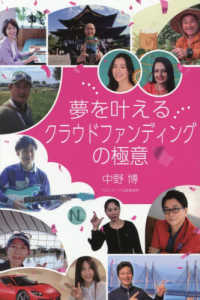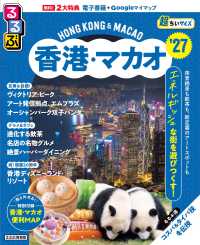内容説明
同じ言葉でも誰がどんな状況で語るかで、その意味は異なり、ときに正反対に受け取れる。このラズノグラーシエ=異和こそがドストエフスーを読む鍵となる。登場人物は対話の中で絶えず異和と不協和に晒され、そのダイナミズムが読む者を強烈に惹きつけるのだ。批評家バフチンを起点に、しかし著者単独で小説内部に分け入り、文学的核心を精緻に照射する。ドストエフスキー論史の転換点を成す衝撃的論考。
目次
まえがき
序 章 ラズノグラーシエ──二葉亭四迷とバフチン
第一章 黄金時代の太陽──『悪霊』
第二章 ソーニャの眼──『罪と罰』
第三章 マリヤの遺体とおとなしい女──『作家の日記』
第四章 写真の中の死、復活、その臭い──『白痴』
第五章 逆遠近法的切り返し──『未成年』
第六章 カラマーゾフのこどもたち──『カラマーゾフの兄弟』
参考文献
単行本あとがき
著者から読者へ
年譜
著書目録
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
遥かなる想い
148
文豪ドストエフスキー論である。 読者を無視したような分量に圧倒された、というのが正直な感想である。 人間の醜悪な部分を なぜ ドストエフスキーは 類い稀な 残酷な能力で描き続けたのか? 著者の饒舌な記述が 邪魔をして、私には わかりにくかったのが 少し残念。 2019/11/04
風に吹かれて
15
「自分を愛するように他者を愛せよ」ということが如何に苦しく困難なことか。そこには「どのような他者でも」という限定条件=無限定条件が付きまとう。真にそれを成し遂げたのは磔刑に処せられたキリストのみだろう。キリストのようなイノセントな少年たち。『カラマーゾフの兄弟』の少年たちの行く末を、ドストエフスキーはどのように「第二の小説」で構想していたのだろう。「自分を愛するように他者を愛せる」のはキリストのみかもしれないが、⇒2017/08/16
悠
4
ドストエフスキーは、どんな理想をいだいて創作にいどみ、その格闘のはてに何を見出したのか。著者は、登場人物たちの表情やしぐさ、言葉づかいや臭いを手がかりに、めまぐるしい心の転変をたどることで、対話の当事者だけでなく作家の企図をも裏切ってゆく事態にたち至る。たがいに同じ言葉を口にしていても、どうしようもなくずれてしまうもの、人と人との間に生じる“異和”との対峙は震撼ものだ。愛すべき人物ばかりじゃないのに、高い理想との落差にもだえ苦しむ“人間的、あまりに人間的”な姿がいとおしくなる、ドストエフスキー論の金字塔。2016/04/30
犬猫うさぎ
1
人間を描いている以上、作者であれ、語りがニュートラルで透明だというただそれだけの理由から自分の内的なモノローグに土足で踏み込んで来ることを平気で許すようなそんな作中人物をドストエフスキーは考えることができなかったのだ。作者であっても、それを記せばその記述行為自体がその作中人物の言動に不可測な干渉を及ばさずにはいないと感じていたのである(…)作中人物の意中の言葉と全く同じであっても、それを作者が書けばその作中人物本人には全く違ったものとして響くはずだからである。(249-250頁)2023/11/18
たかっさ
0
川上未映子さんのエッセーで紹介、というか、軽く触れていた本。2023/01/27
-
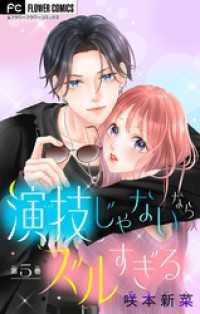
- 電子書籍
- 演技じゃないならズルすぎる【マイクロ】…
-

- 電子書籍
- わたしたちの図書館旅団