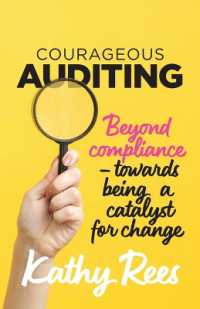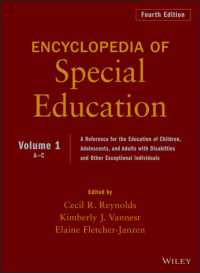内容説明
1分1秒を争う過酷な状況で求められる思考と行動とは? 附属池田小事件、福知山線脱線事故、毒入り餃子事件。多くの命を救ってきた救急医が、そのとき、医者、患者、家族が何を考え、どう行動するかを語る。どんな人にも、苦渋のなかで判断しないといけない場面があり、それは誰にも避けることができません。ご自身あるいはご家族が瀕死の状況に陥ったときどうするのか。私たち医者も、自分たちの死の際を思いながら、毎日仕事をしています。それでも答えは出ません。でも、答えが出ないなりに考え続けています。その過程を少しでも共有できたら、ヒトの死と生を知ることに繋がるのではないか――。本書が少しでもそのお役に立てることを願ってやみません。――「はじめに」より【目次】第1章 患者からしか学べない/第2章 救急医になるのはこんな人/第3章 あの事件の裏側で/第4章 救急医の判断力を支えるもの/第5章 救急医の死生観
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
103
救急医の活躍が書かれて本ではない。著者が生死、事故などに向き合ったときにどんなことを感じて医師としてどう判断して何をすべきか目指すかが書かれている。救急医といえばアメリカドラマERが有名だがドラマの中でも様々なドラマがある。よく詩を覚悟する場面がでてくる。ほんとうにしというものを深く捉えているのかなと感じていたがこれは当事者でないと分からない苦労もあるのだろう。ERといってもアメリカと日本のあり方や宗教感の違いもある、しかし日本のこの手のドラマはERから大きな差が感じられる。そんなことを思い出しながら。2023/01/05
五月雨みどり
10
オットコマエな女医の救命救急奮闘記。激務で一分一秒を争う現場でも,常に患者に寄り添おうとする姿勢に感服。2020/12/25
小豆姫
6
救急医をめざす若者たちが増えてほしい。2018/01/19
Kentaro
5
ダイジェスト版からの要約 「先生はなんでいつも冷静でいられるんですか」。そう聞かれたことがあります。興奮状態にあり、テンションが高い指導医のもとでは、おそらく周りの若い救急医の働きに支障が出るでしょう。「しようもないこと言ったら怒られそう」「余計なことをしちゃいけない」。そう若い医者を萎縮させてしまうかもしれません。それは患者さんに著しい不利益をもたらします。緊急時だからといって、特別な事をする必要はありません。心がけるのは「いつも通りのパフォーマンス」、それが結局、ベスト・パフォーマンスを生み出します。2018/04/10
coldsurgeon
5
救急医が成長の過程で、どのような判断をするようになったかの話である。医療の現場で、医学的に正しい医療を行うことを大切と考えるが、許されない正しさがあるということには、薄々と気づいている。もう助けられないと思う時、延命するのも延命しないのもどちらも正しい。医師にとって自分の死を常日頃考え、それを表面に出さずして、他者の死を語ることができるかが、求められる。医療者はもとより、そうでない人も、家族と死について語ることが重要な時代になってきた。2016/09/05
-

- 電子書籍
- 漫画パチンカー 2022年6月号