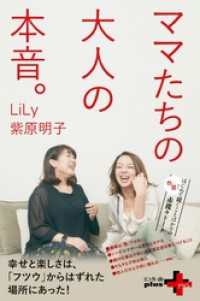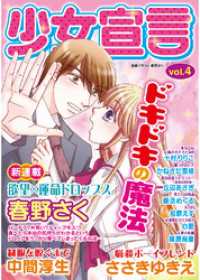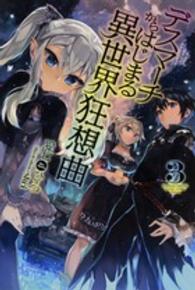内容説明
「福島難しい・面倒くさい」になってしまったあなたへ─ 福島第一原発事故から4年経つ今も、メディアでは放射線の問題ばかりがクローズアップされている。しかし、福島の現実は今どうなっているのか、そして、福島の何を今語るべきなのか? 『「フクシマ」論』で鮮烈な論壇デビューをはたした社会学者・開沼博が、福島問題を単著で4年ぶりに書き下ろし。人口、農林水産業、観光業、復興政策、雇用、家族、避難指示区域……。福島を通して、日本が抱える「地方」問題をもえぐりだした一冊。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいろ
30
ボランティアに入った人が知人にも職場にもいるけれど福島ではない。なんだかタブーの地なイメージが私の中にあって。著者による、福島に対する世間のイメージってこうでしょ!に当てはまってます。はい。読んでわかったのは、福島の問題とされていることの多くは日本全体の各自治体が抱えている問題でもあるってこと。いくつかのキーワードを並べて福島を語るとわかった気になるけど、本当に今住民が求めていることとズレがあるってこと。地元目線で発信できる人の声を聞いて、善意の押し付けじゃない支援。考えさせられる。入門編でわかりやすい。2016/06/13
あやの
30
住んでると体感的に解るような内容がほとんどだったが、やはり、全国向けにはここから説明しないとダメなんだなと、逆にびっくりした。確かに全国放送では取り上げないものね…でも、改めて「そういう見方があるのか!」と発見できたこともあり、有意義な本だった。現実をデータを基に解説していて解りやすい。遠くに住んでいる人ほど「福島だいじょぶ?」と思うだろうけど、それなりにやっている。ただ、データからだけでは見えない住民の微妙な心理的な部分はあまり触れてない。2016/02/22
1.3manen
30
話し言葉で書かれている。本書の目的:福島の問題について論理とデータを通した議論のベースの再設定(34頁)。イメージとは逆に、震災後、県外に流出していた人も戻りつつあるという(40頁)。データを見るべきであろう。重要箇所はゴシ太。人口減少も、意外ともちこたえているというのがデータで見えることらしい(48頁)。福島では人口が増えている(74頁~)。これはイメージとは真逆。人が住んでいない地域でも農業再開、出荷し始めている(117頁)。セシウム対策としてカリウムを撒布しているようだ(120頁~)。2015/06/21
ぐうぐう
28
目が醒めるような福島論だ。メディアが紋切調で伝える福島の姿。学者が物知り顔で語る福島の実態。曰く「福島からは人口流出が止まない」「農地が放射性物質で汚染されたので、破産する農家が増えている」「福島では失業者が続出している」等々。それらがいかに根拠のない言説で、事実とかけ離れているかを、開沼博は詳細なデータと取材により、丁寧に訂正していく。どうしてこのようなデタラメが流布されたのか。開沼は、他の被災地に比べ福島の問題は複雑で面倒くさいからだと説く。(つづく)2015/09/28
おさむ
24
あの震災から4年が過ぎたいまの福島を見つめ直し、学び直す好書。米の生産量や魚の水揚量、木材の生産量、地域の被曝量、観光客数等々、具体的なデータに基づく説明は説得力あり。ステレオタイプに陥りがちな思考を戒めてくれます。フクシマを「買う」、フクシマに「行く」、そしてフクシマで「働く」の好循環を地道に作っていければいいですね。2015/06/19