内容説明
授業づくりでも学級づくりでも、「子どもが動きたくなるような仕掛けをすること」で、子どもは必ず変身していく――教師生活30年超、筑波大学附属小学校の田中博史先生が「クラスをまとめる秘訣」を大公開。学級経営について考えたい先生、必読の一冊です!
目次
はじめに 1
第1章 子どもが変わる最初の一歩
――仕掛けて、待つ
「子どもが自分で考える場」をつくる教師の仕掛け 12
最初は、あえてあいまいな指示を出す 16
友達の「いいところ」を見つける子に育てるために 21
「人づき合いは、見方一つでガラリと変わる」 24
子どもたちへの「根回し?」も教師の仕事 28
「男女の壁をなくす」ことのすごい効果 32
子どもがつくったルールでクラスを動かす 36
ワクワクするモチベーションを生かす 39
日記の見方―返事を要するものはお泊まりさせない 41
ドリルの採点法―低学年から自分で丸をつける方法を教える 44
第2章 「点」ではなく「面」で見る
――子どもを見る
実践! 「子どもウォッチング」のすすめ 48
子どもを「点」ではなく「面」で見る 51
事件は「休み時間の終わり」か「掃除時間」に起きている 55
子どもから信頼を得るための「三回の法則」 59
子どもを変えるのは難しくない? 62
子どもは三日で変わる可能性をもっている! 65
自信をもつと、子どもは自ら変わっていく 70
グループの輪に入っていけない子どもがいたら…… 73
子どもを「見る」ヒントを子どもにもらう 77
ほか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
江口 浩平@教育委員会
12
【学級経営】2016年2月6日の講座の前に著書を拝読。一つ一つの教育的な行為について、とても緻密に計算した上で実践していることがうかがえた。①自分が嬉しいと思うことを子どもにも返す。→シンプルな心構えだが、意外とできていないことを痛感。②先生が提示する「たとえば」というのは、その後のクラスを動かす一つの方向性。→最初から子どもに委ねるのではなく、教師が示したものに子どもたちが共感し、自らやってみたくなるよう仕掛ける必要がある。2016/02/03
しげ
5
子どもの話す力を育てるためには「場に参加する気持ちを育てる」ことが大切。議論をするときは、まず自分の立場を決めること。算数授業の中で、分数の特徴を「相手に合わせて自分を変えるなんて健気なヤツだね」など、人の性格に例える方法がとても面白く、理解しやすかったです。2024/01/29
あべし
3
主に3つの学びがあった。 ① 子どもウォッチング ② ささやき戦術 ③ ほめ方三段ロケット どことなくほめれば良い、みたいな感覚で子どもと接していたかもしれない。最近、「ほめるなら具体的にほめよ」といったことをよく聞くようになった。上っ面だけの「すごいね」などは、だんだんと子どもたちの心には響かなくなる。下手すると「操作しようとしている」という印象ももたれてしまうらしい。 子どもはおそらくそこまでは考えていないだろうが、ただ子どもだって人間。考えはしなくとも感じてはいる。 具体的にほめよう。2020/08/05
y
3
早速実践。効果があるとかないとかは置いといて、そんな優しい接し方、迫り方があるのかと一つ学んだ。大げさなことはなに一つ必要ないと。2018/11/01
2h35min
3
算数教育で有名な人なんですが、こんな本も書いてたんだ。 「発表してる人にからだを向けて」という「授業規律」より「なぜ発表者にからだを向けないといけないのか」という「必然性」を教えることのほうが重要。 納得。2018/01/03
-
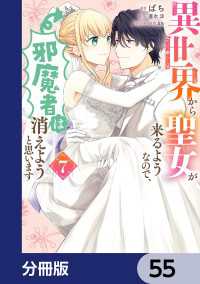
- 電子書籍
- 異世界から聖女が来るようなので、邪魔者…
-
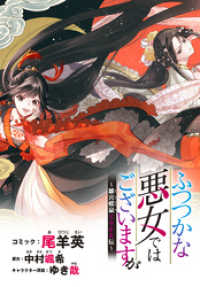
- 電子書籍
- ふつつかな悪女ではございますが ~雛宮…
-
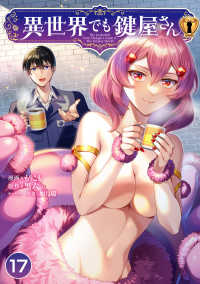
- 電子書籍
- 異世界でも鍵屋さん【単話版】 / 17話
-
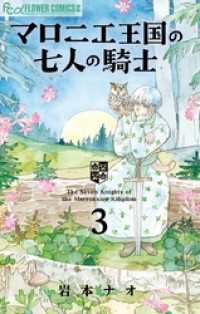
- 電子書籍
- マロニエ王国の七人の騎士(3) フラワ…





