内容説明
なぜわれわれはかくも多彩なものを恐れるのか? ときに恐怖と笑いが同居するのはなぜか? そもそもなぜわれわれは恐れるのか? 人間存在のフクザツさを読み解くのに格好の素材がホラーだ。おなじみのホラー映画を鮮やかに分析し、感情の哲学から心理学、脳科学まで多様な知を縦横無尽に駆使、キョーフの正体に迫る。めくるめく読書体験、眠れぬ夜を保証するぜ!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
keroppi
69
「悪魔のいけにえ」「スクリーム」「ゾンビ」「SFボディスナッチャー」「シャイニング」「ザ・フライ」「リング」「サイコ」等々、ホラー映画を取り上げながら、なぜ人間は、ホラーに恐怖するのか、なぜ怖いホラーを見るのかを、哲学的に解き明かしていく。ホラーを語る時の軽妙さと、学術的な哲学論の説明が、ごちゃ混ぜだが、それが楽しくて、ぐんぐんと読み進めてしまった。恐怖というのは、実に奥深い。2019/08/28
ころこ
39
大陸哲学と分析哲学があるように、ホラーを論じるのも、大陸哲学型の精神分析を軸とした文化論と、分析哲学型の認知科学的な分析に大別できます。本書は分析哲学型が中心です。大陸系の精神分析では、要するに「最も怖いのは自分」という結論がみえていて、あまりにも単純です。分析系のアプローチは、一歩間違えると、単なる映画の表現論になってしまいそうですが、ノエル・キャロルのホラーの定義から始まる第Ⅱ部の分析はまとまりの無いものの、色々考え、検討しならが読めました。「なぜ、ひとはホラーを欲望するのか」は7章で検討されています2019/05/10
kana
19
端的にいうとホラーってなぜエンタメなのか?について紐解く哲学の本で、先行研究も丁寧に紹介され、思ったより骨太。本題に入るまでにそもそも怖いって何?ホラーって何?を定義するためにページの3割を割いていた。テクノロジーの影響は受けても人間自体が劇的に進化するわけではないから、その本質に迫らんとする感じにわくわくしました。実際にどこまで迫れたのかというと理解が難しい部分もあったのだけど、恐怖を感じる認知の方程式的なものはなるほど!と思いました。2023/10/29
テツ
17
哲学者である著者がホラー映画について思考を積み重ね論じる。恐怖という感情はストレスでしかない筈なのに何故それを能動的に求めてしまい、快楽として消費できるのか。そもそも作り物であることは明々白白な作品群に対して何故恐怖を感じるのか。ぼくもいわゆる怖い話は大好きだけれど幽霊的な怪異を全く信じていないので単純に読み物として好んでいる。なので恐いと感じることはほぼなく、そのために恐怖を楽しむという行為自体がいまいちピンとこないけれど、それを快楽とするメカニズムだけはうっすらと理解できた気がします。2023/05/23
H2A
14
自分はホラー映画が極端に苦手で今でもまともに観ていられない。よく知らずに見はじめた映画(ティム・バートンの『スウィーニー・トッド』)で途中退席したこともあるぐらい。この本は哲学者というわりにはくだけた文章だけれど、内容は相応に理屈っぽく分析してくれる。分量も結構あって原初的な情動について少し客観的な視点を得られたような気がする。2021/11/28
-
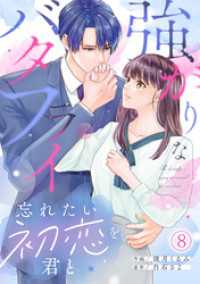
- 電子書籍
- 強がりなバタフライ~忘れたい初恋を君と…







