内容説明
かつて家族にとって絶対的な存在であった父親は、共同体の崩壊とともにその役目を少なくしていった。 しかし、父親との葛藤から開放された子どもたちは母親との密着を強め、精神の安定を得るどころか人間関係の構築に支障を来たし始める。 現役精神科医である著者がヘミングウェイやガンジーといった偉人や膨大な実例をもとに父親が果たすべき役目とその変遷、「父親の不在」から、知らぬ間に現代人を蝕む病の正体と救済の道を探る。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
青蓮
74
ノラさんからのお勧め。以前同著者の「母という病」を読んで「父親はどうした?」と思ったらこちらの本が出ていました。時代と共に家父長制が解体され父親の存在が希薄になっていくに従って母子が際限なく緊密になり、その癒着が子の親離れ、自立を阻害しているという。失われた父親、理想の父親像を求める子は人間関係に躓いたり、下手をすると精神的にかなり不安定になってしまう。子供の健全な発達にはそれが例え代理的なものであっても父なるもの、母なるものが不可欠だ。憎しみながらも愛したいという子からの親のへの希求は切ない程だ。2019/09/20
べるめーる
30
「母という病」に続いて読了。前作では母という立場で生まれる病理に大きなインパクトがあったが、本作は父親ならではの病理というよりも、父親の役割や、不在や疎外がどう影響するかといった内容だった。DVや浮気などの問題行動も結局は夫婦関係だとすると、妻がうまく機能すれば解決するものなんだろうか。離婚して子育てしているので、不在の影響がとりわけ気になる。不在だからこそ理想化したり、求めたりする気持ちが膨らんでいくのが切ない。母という病の深みにはまって、娘の気持ちを歪めないように、自分を律していかなくてはと思う。2015/05/09
ひろ☆
24
家族環境が子供に与える影響、片親不在だけならまだしも、両親からの愛情を感じられなかったら、トラウマになるし、ずれた価値観にもなるよな。ただ、それをバネにして、名を残す人になった人もたくさんいる。子供と父、母の関係もそうだし、父母の関係が子供に与える影響も大きいし、わかっているけど、難しい。女性の性格を知りたかったら、両親との関係を聞くのがいいのかもな。2015/04/17
ミッキー・ダック
22
父親の存在感が希薄な「父親不在」の時代にあって、父親の役割の重要性を説く。子どもが母親とさえ不確かな関係しか持てない現代の病理を明かした「母という病」の続編だが、実は「母という病」は父親不在と表裏一体だという。母親は、乳幼児期の愛着形成により子どもの存在基盤となるが、父親は、成長期には母子分離を助け、世の中の掟や遊びを教え、思春期には社会への導き手となって、子どもの健全な成長を促す。父親不在による様々な母子関係・父子関係の病理を、具体的な事例をあげながら解説している。著名人の例が多く興味深い。 2015/01/25
♡kana*
19
複雑だよなぁ。やっぱり、夫婦が揃っていることは大切。2015/03/20
-

- 電子書籍
- 走れ!ウンコオー【単話版】40話 うん…
-
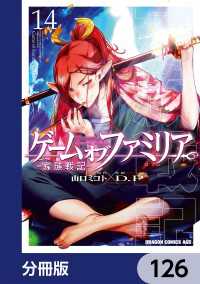
- 電子書籍
- ゲーム オブ ファミリア-家族戦記-【…
-
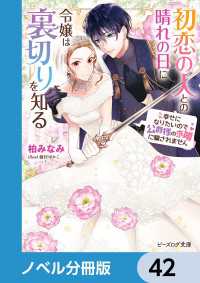
- 電子書籍
- 初恋の人との晴れの日に令嬢は裏切りを知…
-
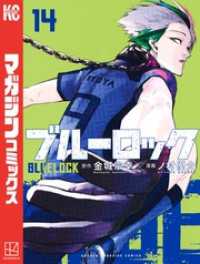
- 電子書籍
- ブルーロック(14)
-
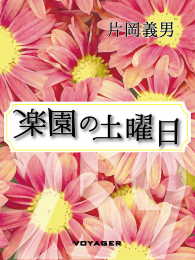
- 電子書籍
- 楽園の土曜日




