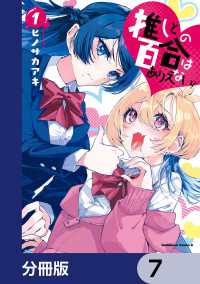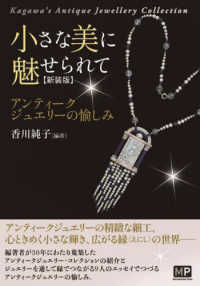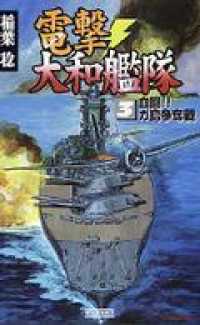- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
「開国か攘夷か?」「尊皇か佐幕か?」――もはや一刻の猶予もない欧米列強の脅威と、ひたひたと忍び寄る植民地化の危機。日本の行く末を案じ、また己の権力の増強を目指して、幕府や大名、そして維新志士たちが動乱の時代を駆け抜けた。しかし、ある者は権勢を振るった末に消え、ある者は“時代の先駆者”のまま早々に舞台から降り、またある者は、維新を完遂したところで権力を奪われた。本書は、政治学者の著者が、幕末人物たちの「強大な政治力が失われる過程」を考察することで、現代にも通じる“失敗の教訓”を学ぶ。「徳川幕府が気づかなかった売国への道~井伊直弼と田中角栄」「生き残った山内容堂、殺された坂本龍馬」「『真珠湾攻撃』なき戊辰戦争で失敗した、松平容保」「西郷隆盛にとっての、『島津久光』という失敗」「水戸藩と長州藩、維新さきがけの組織疲労」など、彼らが“新時代”から姿を消した理由がここにある!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
死んだらシリウスへ行きたい
80
徳川幕府260年の太平、幕末期、侍はもう侍ではなくなっていた。ただの地方公務員、農工商の上に無為徒食で胡坐をかいた無用の存在、多少、行政的文化的に貢献できた程度、西洋列強の武力の前に、あっさりと方針転換、それに対抗できる体制づくり。その必要性に対応できた各藩、必要性は理解しても永年の義理や恩顧から滅んで行かざるを得なかった藩、いろいろあった。薩摩長州から京都へ、道中多くの親藩・譜代が道を開け、先導を務めた。最後、江戸に至るまで、どう生きたか、どう対処したか、面白い内容だった。我々なら、どうする。2024/03/20
糜竺(びじく)
24
理想を現実にするには、正しさよりもまず、政治力が必要。幕末の歴史を通して、その政治力とは何かが学べた。2022/02/11
maito/まいと
13
幕末に関しては類書が多い中、バシッと筋の通る論調の本が欲しかった。この本はそんな希望に応えてくれた1冊。分析や挿話ではなく、幕末という時代のどこに目を付ければいいのか?何を学び何を取り入れればよいのか、この本読むとよくわかる。群像激が注目されがちな幕末に、落ち着いた目線できちんと学びを得たい人にはオススメ。2015/03/02
岡本
7
前作・戦国編に続き購入。幕末において動きを起こした大名の行動を政治力に関連付けて読み解く一冊。一般的に暗愚等の批判的な評価のある大名等の評価を考えなおしたり、逆に評価の高い英雄を見なおしてみたり。組織における個人やリーダーに必要な能力、組織全体の動かし方など現代の社会人に必要な考え方も纏められています。2015/06/14
クラッシックラガー
5
どストライク。幕末の要人を通して現代の政治を見る。政治部分は、なるほどの範囲で活かすところない現状。組織論、リーダー論が幕末メガネで読ませるところが、解り易い。どストライク。巻末の参考文献の数、あれだけ読んでエッセンスを抜き出すんだから、超お得ね。私も何冊かは読まないと…と、瀧澤さんのをおかわりしてからだな。2015/06/08


![お役立ちICU看護カード [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/47965/4796570101.jpg)