内容説明
秩禄処分とは、明治9年、華族・士族に与えられていた家禄を廃止し、「武士」という特権的身分を解体した変革である。現代にたとえれば、公務員をいったん全員解雇して公職を再編するようなこの措置は、なぜ、曲折を経つつも順調に実施され、武士という身分はほとんど無抵抗のまま解消されたのか。江戸時代以来、「武士」はどのように位置付けられ、没落する士族たちは、新たな時代にどう立ち向かっていったのかを明らかにする。(講談社学術文庫)
-
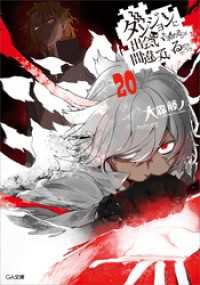
- 電子書籍
- ダンジョンに出会いを求めるのは間違って…
-
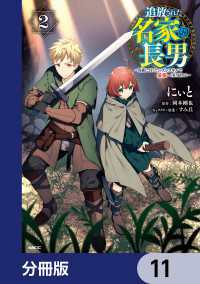
- 電子書籍
- 追放された名家の長男 ~馬鹿にされたハ…
-
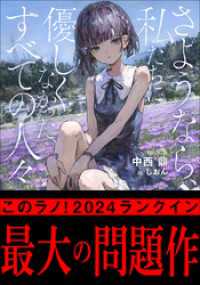
- 電子書籍
- さようなら、私たちに優しくなかった、す…
-
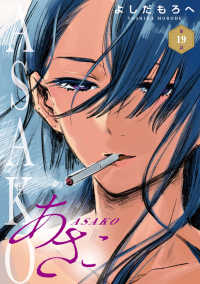
- 電子書籍
- あさこ(話売り) #19 ヤンチャンL…




