- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
地域再生のためには、地域住民が内発的に立ち上がるしかない。ではそれはいかにして可能か。住民・行政・NPOの連携・協働の仕組みを理解した上での住民のワークショップが鍵となる。「寄りあいワークショップ」の技法を開発し、日本各地で実践してきた著者が、数多くの成功例を紹介。子供から年寄りまで、住民の誰もが参加し、連帯感をもってアイデアを出しあい、地域を動かしていく方法を伝授する。どこの地域でも、どのような立場でも役立つ地域再生の原理と方法の入門書。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
28
筆者の主張:課題解決組織を再び自治コミュニティに再構築(073頁)。寄りあいワークショップには、内発力に火をつける力がある。付箋紙に意見を書き、模造紙上に貼ってマジックで描画(080頁)。潜在力といってもよかろう。内発的潜在力であろう。これが民主主義じゃないのかな。これが市民社会ではないかな。手順として、意見地図⇒資源写真地図⇒アイデア地図(085頁)。YW第一原理:問題の解と合意の創造が対になっているのが内発的地域再生を導く。2016/02/20
*
17
瀬戸内海の離島で80代の議員が「冥土の土産に橋がほしい」と発言した話は、もうまるっきり湊かなえ『望郷』の世界だ。建設至上主義の行きつく先は、若者の流出に犯罪の流入。病院との距離だけは改善されたけど・・・▼地域の「あるもの探し」ブレストでは、住民が持ち寄った写真を積極的に活用していた。これなら外国人や、小さな子供でも参加できる余地が広がる。自分なんかはせっかくイベントを企画しても、写真という記録を残しておくのをつい忘れてしまうので、改めて反省。2018/08/14
三上 直樹
4
「地方消滅」論に対抗して、寄り合いワークショップによる地域の自立を進めてきた著者の論考。陳情型になって自律性が失われていると指摘される現実と向き合いながら何とか生きのびていく方策をさぐっている自分にとっては、こういった実践に出会うチャンスがほしいと願っています。2015/12/12
たつのおとしご
2
寄りあいワークショップによって住民主体の地域づくりの実践について書かれている。途中難しい言葉もあり、解読が困難な所もあったが実践をより詳しく調べてみたくなった。2017/02/22
yokkoishotaro
1
内発性というものを取り上げられていたことが大変印象に残った。内発的に課題を出すことが、効率的な政策につながっていくのだと思った。 いい政策とは何かを考える上で、重要な視点だと思った。2021/12/17
-

- 電子書籍
- 母さんの第2巻 1巻 ヤングキングコミ…
-
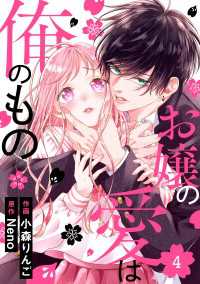
- 電子書籍
- noicomi お嬢の愛は俺のもの(分…
-

- 電子書籍
- ナカのいい女【全年齢版】(1) Rub…
-

- 電子書籍
- ヤンキーJKとワケあり生徒会長 14巻…
-
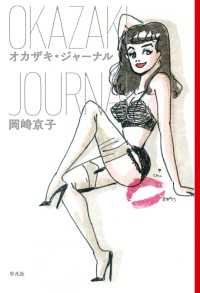
- 電子書籍
- オカザキ・ジャーナル




