- ホーム
- > 電子書籍
- > 教養文庫・新書・選書
内容説明
現代日本の思想が当面する問題は何か.その日本的特質はどこにあり,何に由来するものなのか.日本人の内面生活における思想の入りこみかた,それらの相互関係を構造的な視角から追求していくことによって,新しい時代の思想を創造するために,いかなる方法意識が必要であるかを問う.日本の思想のありかたを浮き彫りにした文明論的考察.
目次
目 次
Ⅰ 日本の思想
まえがき
日本思想史の包括的な研究がなぜ貧弱なのか/日本における思想的座標軸の欠如/自己認識の意味/いわゆる「伝統」思想と「外来」思想/開国の意味したもの
一
無構造の「伝統」その(一)──思想継起の仕方/その(二)──思想受容のパターン/逆説や反語の機能転換/イデオロギー暴露の早熟的登場/無構造の伝統の原型としての固有信仰/思想評価における「進化論」
二
近代日本の機軸としての「國體」の創出/ 「國體」における臣民の無限責任/ 「國體」の精神内面への滲透性
三
天皇制における無責任の体系/明治憲法体制における最終的判定権の問題/フィクションとしての制度とその限界の自覚/近代日本における制度と共同体/合理化の下降と共同体的心情の上昇/制度化の進展と「人情」の矛盾
四
二つの思考様式の対立/実感信仰の問題/日本におけるマルクス主義の思想史的意義/理論信仰の発生/理論における無限責任と無責任
おわりに
Ⅱ 近代日本の思想と文学──一つのケース・スタディとして──
まえがき
政治─科学─文学
一
明治末年における文学と政治という問題の立てかた/文学の世界をおそった「台風」/ 「社会」の登場による走路の接近/マルクス主義が文学に与えた「衝撃」/文学者に焼付けられたマルクス主義のイメージ/昭和文学史の光栄と悲惨/政治(=科学)の優位から政治(=文学)の優位まで
二
プロ文学理論における政治的および科学的なトータリズム/政治的と図式的/政治過程におけるエモーションの動員/政治における「決断」の契機/思考法としてのトータリズムと官僚制合理主義/政治の全体像と日常政治との完全対応関係/方法的トータリズムの典型/政治(=科学)像の崩壊──転向の始点と終点/日本の近代文学における国家と個人/ 「台風」の逆転と作家の対応の諸形態/旧プロ文学者における文学の内面化と個体化/対立物(文学主義)への移行契機
三
文化の危機への国際的な対応/各文化領域における「自律性」の摸索/政治・科学・文学における同盟と対抗の関係/科学主義の盲点/トータリズムの遺産の否定的継承/ 「意匠」剥離の後に来るもの
おわりに
Ⅲ 思想のあり方について
人間はイメージを頼りにして物事を判断する/イメージが作り出す新しい現実/新しい形の自己疎外/ササラ型とタコツボ型/近代日本の学問の受け入れかた/共通の基盤がない論争/近代的組織体のタコツボ化/組織における隠語の発生と偏見の沈澱/国内的鎖国と国際的開国/被害者意識の氾濫/戦後マス・コミュニケーションの役割/組織の力という通念の盲点/階級別にたたない組織化の意味/多元的なイメージを合成する思考法の必要
Ⅳ 「である」ことと「する」こと
「権利の上にねむる者」/近代社会における制度の考え方/徳川時代を例にとると/ 「である」社会と「である」道徳/ 「する」組織の社会的擡頭/業績本位という意味/経済の世界では/制度の建て前だけからの判断/理想状態の神聖化/政治行動についての考え方/市民生活と政治/日本の急激な「近代化」/ 「する」価値と「である」価値との倒錯/学問や芸術における価値の意味/価値倒錯を再転倒するために
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はっせー
kaizen@名古屋de朝活読書会
yomineko@💖ヴィタリにゃん💗
SOHSA
佐島楓
-
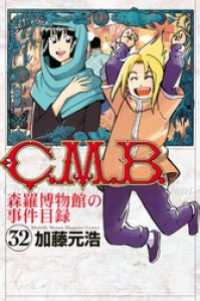
- 電子書籍
- C.M.B.森羅博物館の事件目録(32)
-
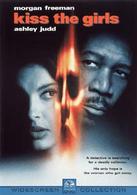
- DVD
- コレクター







