内容説明
地方消滅と名指しされた村を「守る側になる」と増えたIターン・Uターンの移住者.地元合意に立脚してプライド高き商店街を再生した,まちづくり株式会社.自然エネルギーや有機農業で半農半Xを推し進めるビジネスマインドのNPO――経済成長よりも共感に軸をおく人々のチャレンジは止まらない,その最新の現場報告.
目次
目 次
はじめに
序章 移住が増えてきた「消滅市町村」第一位の村──群馬県南牧村
増田レポートの衝撃と誤り/年少人口率も高齢化率も日本一の村/村の将来を若手中心で考える/移住者が増えてきた/昔のままの姿に魅せられて/環境循環農法で野菜を作り、文化を守っていきたい/都会にしかないものは、何もない/増田レポートは乗り越えられる/動き出した自治体行政/変化が見えてきた
第1章 山村に希望あり──島根県邑南町・旧弥栄村・旧柿木村
女性と子どもが輝くまちづくり/A級グルメのまちづくり/耕すシェフと地域おこし協力隊の活用/移住者への手厚いサポート/トップランナーの課題/山村の暮らしに惹かれる若者たち/暮らし型有機農業と産業型有機農業/生き方志向と農業志向/兼業起農の意義と挫折/有機農業の村づくり/半農半Xが地域を支えていく/有機農業は環境保全型農業の延長ではない/農林大学校に有機農業専攻を設置/半農半Xを応援する/GNPからGLHへ
第2章 自然エネルギーが地域を開く──福島県会津地方、岐阜県石徹白地区
自然エネルギー電力会社の設立/基本ソフトを書き換える/一年半で合計二・五四MWの太陽光発電所が完成/積雪への対応/想いがつまった公共的株式会社の経営/一歩後退した小水力発電/手作りの水車でのライトアップから/事業の多様化と小売りのイメージ/人口が半世紀で四分の一に/マイクロ水力発電を活かした地域づくり/小水力発電所を運営する農協をつくる/成功のポイント/地域づくりの課題
第3章 漁業者とNGOの協働で地域を結い直す──宮城県旧北上町、福島県相馬市
死者・行方不明者は人口の約八%/漁協主導で復興へ/株式会社で販売まで手掛ける/協業化は広がるのか/地域漁業を誰がどう担うのか/NGOが果たした役割/模索しながら活動を続ける/被災者が被災者を支援する/それでも前を向く/リーダーの模索/NPOを基盤に多面的な活動
第4章 地域再生の柱としての商店街──香川県高松市、宮城県丸森町大張地区
殺到する視察者/老舗商店街の劇的な衰退/元凶はバブル/土地の所有権と利用権の分離を実現/街区ごとのコンセプトと仕組み/おとなのファンシーショップはわずか五坪/ハイレベルな“自治会立”診療所/地場産食材の適正な流通/商店街の自給自足/ここで暮らせて本当によかった/再開発事業への投資と効果/これからめざすまちづくり/中心市街地の活性化は農地の再生でもある/住民の七割が出資した「共同店」/売り上げは三割減でも、店はなくせない
第5章 NPOが創り出す、ゆうきの里──福島県旧東和町
地域を担う主体/放射能に対峙/土の力で放射能を抑え込む/自給的農を保証し、生きがいを創り出す/複数のリーダーたち/キャリア官僚からの転身/震災直後に来て農業で自立へ/半農半農家民宿/新規就農者をみんなで支える/震災から自力で立ち上がる/福島有機ネットの役割と意義/NPOと行政の協働/ゆうきの里の課題
第6章 有機農業と地場産業の連携による地域循環型経済の誕生──埼玉県小川町
有機農業の意義と現状/安定した有機農業の確立と新規就農者の増加/地元の米で造るから地酒/小規模農家を守る価格で大豆を買い上げて豆腐を作る/集落への広がり/企業版CSAの実現と集落皆有機の達成/町内での有機野菜の流通ルート/むらとまちを結ぶコーディネーター
あとがき
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
えも
メタボン
ひかりパパ
skunk_c
-

- 電子書籍
- 悪役の幼馴染として生き延びる【分冊版】…
-
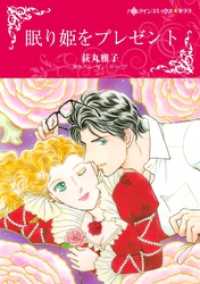
- 電子書籍
- 眠り姫をプレゼント【分冊】 10巻 ハ…
-

- 電子書籍
- 死に戻り、全てを救うために最強へと至る…
-
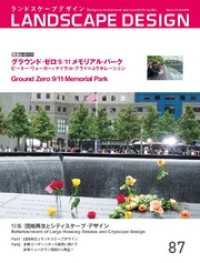
- 電子書籍
- LANDSCAPE DESIGN No…
-
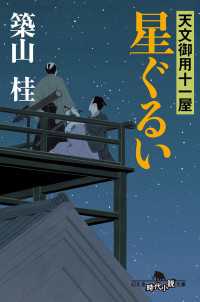
- 電子書籍
- 天文御用十一屋 星ぐるい 幻冬舎時代小…




